こんにちは、ハルです。
「禁酒、始めたはいいけど、やっぱり飲んじゃった…」 「仕事のストレスでお酒が頭から離れない…」
もしかして、今そんな風に感じていませんか?
僕も、禁酒を始めたばかりですが、何度も飲酒欲求に襲われました。冷蔵庫を開けるたびに頭にお酒が浮かんだり、仕事で嫌なことがあると「もう一杯だけ…」と心が揺らいだり。
でも、お酒が頭に浮かぶ「隙」を与えない3つのコツを知ってからは、飲みたい衝動に襲われることがグッと減りました。
- 禁酒はしたいけど、なかなか一歩を踏み出せない方
- 飲酒欲求に負けて、いつも挫折してしまう方
- 禁酒を「我慢」だと捉えていて、ストレスが溜まっている方
 ハル
ハルこの記事を読めば、飲酒欲求が湧いたときの具体的な対処法が分かります。そして、無理なく楽しく禁酒を続けるためのヒントが見つかりますよ。
「飲みたい」という飲酒欲求はなぜ生まれるのか?
まず、なぜ「お酒を飲みたい」という欲求が生まれるのか、その根本的な原因を知っておきましょう。
それは、無意識に繰り返されている「習慣のループ」が関係しています。
たとえば、僕の場合だとこんな感じでした。
きっかけ
週末の夜、アニメを見ようとすると「暇だな…」と感じる。この「手持ち無沙汰な感覚」こそが、僕にとってのお酒を飲みたくなるサインでした。
行動
気分転換のため、コンビニに買い物に行く。頭の中ではもう、冷たい「こだわり酒場のレモンサワー」を飲むことだけを考えています。おつまみもセットで買えば完璧です。
ご褒美
家に帰ってアニメを流しながら飲むと、頭がぼーっとしてリラックスできる。この「ぼんやりする時間」が最高のご褒美でした。
「お酒が飲みたい」という気持ちは、僕の意志とは関係なく、ただ単に習慣のスイッチが入っただけだったんです。
だから、無性に飲みたくなるのは、あなたの意志が弱いからではなく、習慣のスイッチが入ってしまっただけだと考えられます。
あなたの「飲みたい」という気持ちは、習慣のループによって生まれているだけです。でも、このループを断ち切ることは可能です。
この記事では、僕自身が実践して効果があった、お酒が頭に浮かぶ「隙」を与えない3つの対処法をご紹介します。
- 習慣の「行動」を別のものに置き換える
- 環境を変えて「飲酒のきっかけ」をなくす
- 禁酒仲間を見つけて「孤独な戦い」をやめる



これらの方法を知ることで、あなたはもう飲酒欲求と戦う必要がなくなります。
習慣の「行動」を別のものに置き換える
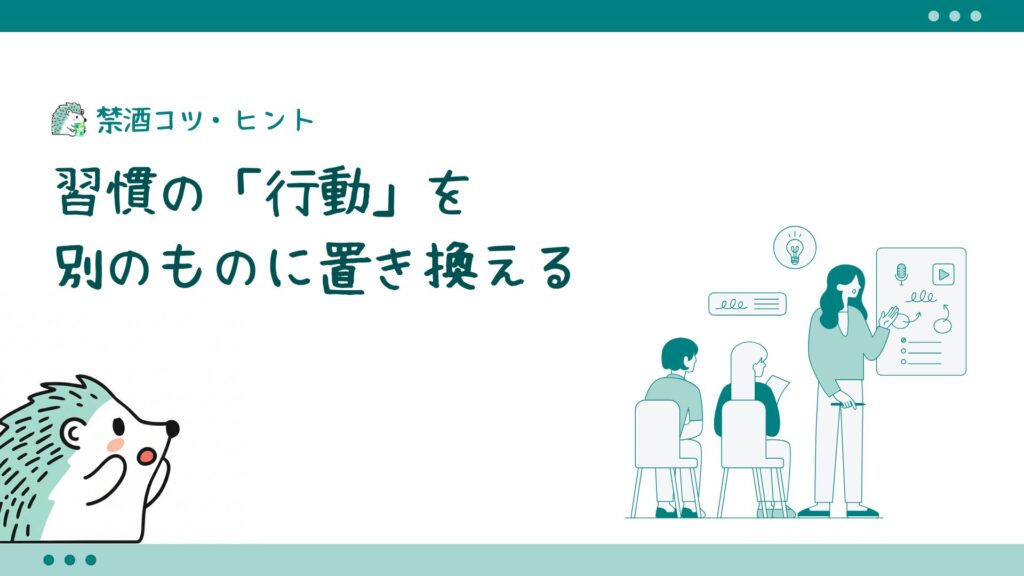
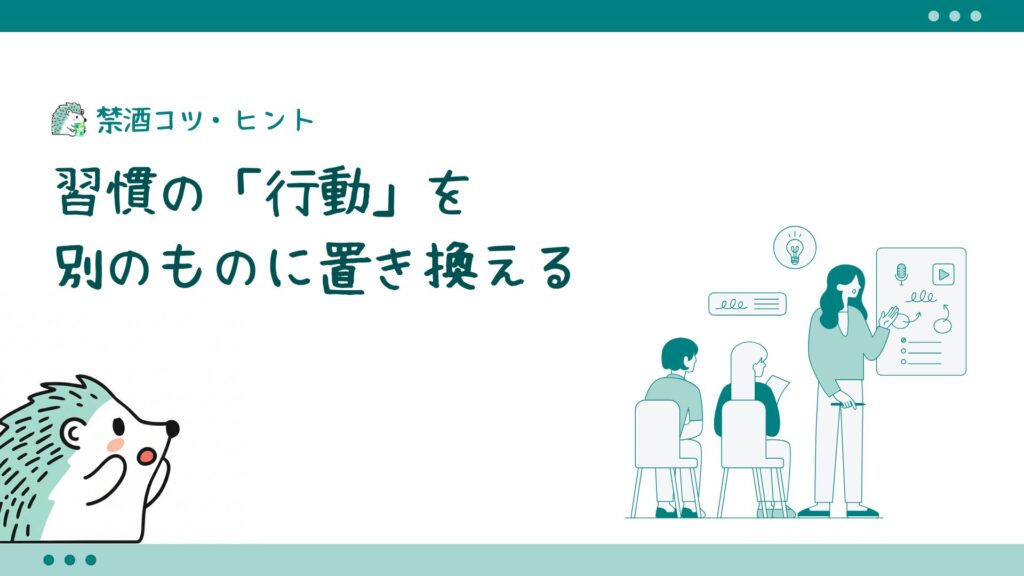
このループを断ち切るには、「行動」の部分を別のものに置き換えるのが効果的です。
僕の場合、禁酒5日目の週末に暇を持て余したことが、まさにこのきっかけになりました。
いつもならアニメを見ながらお酒を飲んでいましたが、お酒がないと時間が持たない。そこで、暇な時間という「きっかけ」に対して、新しい「行動」を試すことにしたんです。
この考え方は、ベストセラー『習慣の力』の著者、チャールズ・デュヒッグ氏が提唱した「習慣のループ(Habit Loop)」として知られています。
- きっかけ(Cue):脳が行動を自動的に始めるための引き金だと言われています。
- 行動(Routine):実際に体が動く、無意識の行動だとされています。
- ご褒美(Reward):行動を終えたときに脳が感じる満足感だと言われています。
このループが繰り返されることで、習慣はどんどん強化されていきます。
この理論を知って、僕の禁酒生活がどう変わったかお話しします。
僕の習慣のループは、【暇だ】という「きっかけ」から始まり、【お酒を飲む】という「行動」で【リラックス】という「ご褒美」を得るものでした。
ご褒美(リラックスしたい気持ち)は変わらないので、「行動」だけを別のものに替えることにしました。
そこで始めたのが、ブログです。最初は「めんどくさい」の一言でしたが、記事を書き進めるうちに「もっとこうしたほうがいいかな?」と夢中になれました。
記事が完成したときの達成感は、お酒を飲んだときの満足感とは全く違いましたが、それ以上に満たされるものがあったんです。
こうして、僕の習慣のループは【暇だ】→【ブログを書く】→【達成感を得る】という新しいループに書き換わりました。
環境を変えて「飲酒のきっかけ」をなくす
飲酒欲求が生まれる「隙」を与えないためには、身の回りの環境を変えることも大切です。
僕が真っ先にやったのは、冷蔵庫からお酒をなくすことでした。家に誘惑がなければ、わざわざ買いに行く手間をかけるのが面倒になり、自然と飲む機会が減ります。
そして、僕にとっての飲酒欲求のきっかけは、アニメを見ながらダラダラ過ごす「暇な時間」でした。この時間を埋めるために、僕はブログを書くことに没頭するようにしました。
お酒を飲んでいた頃は、アニメを見ながら「ながら飲み」をしていましたが、ブログはそうはいきません。
集中力が必要なので、お酒を飲んでしまうと良い文章が書けないんです。そうやって、暇な時間と飲酒の間に「ブログ」という別の行動を挟むことで、飲むきっかけを物理的に断つことができました。
この考え方は、行動経済学の「ナッジ(Nudge)」に通じると言われています。これは、ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー氏とキャス・サンスティーン氏が提唱したものです。
簡単に言うと、「人が無意識に良い選択をするように、こっそり背中を押してあげる」という考え方です。
そして、このナッジを実践するための手法の一つに、「選択アーキテクチャ(Choice Architecture)」というものがあります。
これは、人々がより良い選択を自然にできるように、環境を設計することだとされています。
- タバコが会社の入口にある: いつでも買える状況では、吸いたくなりますよね。
- タバコが奥まった場所にある: わざわざ手間をかけて買いに行く人が減ると言われています。
このように、行動を変える「きっかけ」を作ってくれるのがナッジです。
僕がやった「冷蔵庫からお酒をなくす」ことや、「飲酒と両立できないブログを始める」という行動は、まさにこの「選択アーキテクチャ」を活用した有効な戦略だそうです。
禁酒仲間を見つけて「孤独な戦い」をやめる
禁酒を「孤独な戦い」にしてしまうと、心が折れやすくなります。周りにお酒を飲む人が多いと、「自分だけ我慢している…」と感じてしまいがちです。
僕が実践したのは、SNSで「禁酒アカウント」をフォローすることでした。同じように禁酒を頑張っている人たちの投稿を見ることで、「自分一人じゃないんだ」と安心できます。
- SNSで禁酒仲間を見つける
- ブログのコメントで交流する
- 家族や友人に禁酒を宣言する
誰かと「禁酒」という目標を共有することで、心の支えになります。
社会心理学には「社会的証明(Social Proof)」という概念があります。
これは、多くの人が行っている行動は正しいと感じ、自分も同じ行動を取るようになる心理効果です。この概念は、心理学者であるロバート・B・チャルディーニ氏が提唱したことで知られています。
禁酒仲間を見つけ、彼らが成功している姿を見ることで、「自分もできる」という確信が強まり、行動が後押しされます。
禁酒で得られるメリット・効果
禁酒を始めたばかりの頃は、正直メリットがよく分からないかもしれません。でも、禁酒を続けると、僕たちが思っている以上に様々な良い変化が起こります。
- お金:出費が減って、将来のための貯金や投資ができる
- 時間:二日酔いや無駄な時間がなくなり、自由に使える時間が増える
- 健康:体の内側から調子が良くなり、ダイエットや美容にもつながる
- メンタル:自己肯定感が高まり、自分に自信がつく
- 人間関係:お酒に頼らない、本当の信頼関係を築ける
僕が実際に感じた「禁酒で得られるメリット」について、詳しくまとめた記事がありますので、ぜひ読んでみてください。
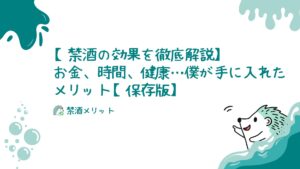
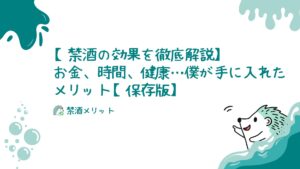
禁酒中のおともには、サントリーオールフリーがおすすめ!!
サントリーオールフリーは、禁酒中の僕にとって、十分すぎるほど満足できる最高の相棒でした。
もちろん、本物のビールとは違うと感じる部分もあります。でも、ノンアルコールでありながらビールの風味を再現していて、我慢ばかりの禁酒生活から僕を救ってくれたのは間違いありません。
特に、「プリン体ゼロ」「カロリーゼロ」「糖質ゼロ」という点も、健康を意識している僕たちには嬉しいポイントです。
サントリーオールフリーのレビュー記事も書いてます。禁酒中にどうしても飲みたくなることもあると思いますが、そんな時はぜひ、サントリーオールフリーを試してみてください!
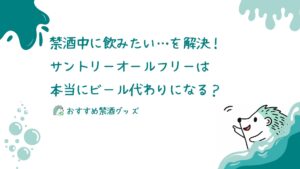
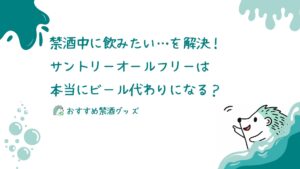
まとめ:禁酒は「仕組み」で変えられる
「飲みたい」という強い欲求は、決してあなたの意志が弱いからではありません。無意識の習慣が引き起こす、ごく自然な反応だと知ることで、少し心が軽くなったのではないでしょうか。
無理な我慢をやめて、今日から「仕組み」を変えることで、飲酒欲求に打ち勝つことができます。
最後に、今回お伝えした「飲酒欲求をなくす仕組み」をもう一度おさらいしておきましょう。
- 行動を変える:暇な時間を、お酒と両立できない「やりがい」で埋める。
- 環境を変える:冷蔵庫からお酒をなくすなど、物理的に飲酒のきっかけを断つ。
- 仲間を見つける:SNSなどを活用し、孤独な戦いをやめる。
僕もまだまだ初心者ですが、あなたと一緒に成長していけたら嬉しいです。
今日から、この記事で紹介した3つの方法のうち、どれか一つでも試してみませんか?
僕もTwitter(X)で禁酒記録を発信しています。同じように頑張っているあなたと、ぜひ繋がれたら嬉しいです。
あなたの決意が、きっと誰かの大きな励みになります。僕のTwitterアカウントです。 よかったらフォローしてくださいね!



僕もまだまだ道半ばです。でも、もしこの記事があなたの小さな一歩のきっかけになれたなら、とても嬉しいです。
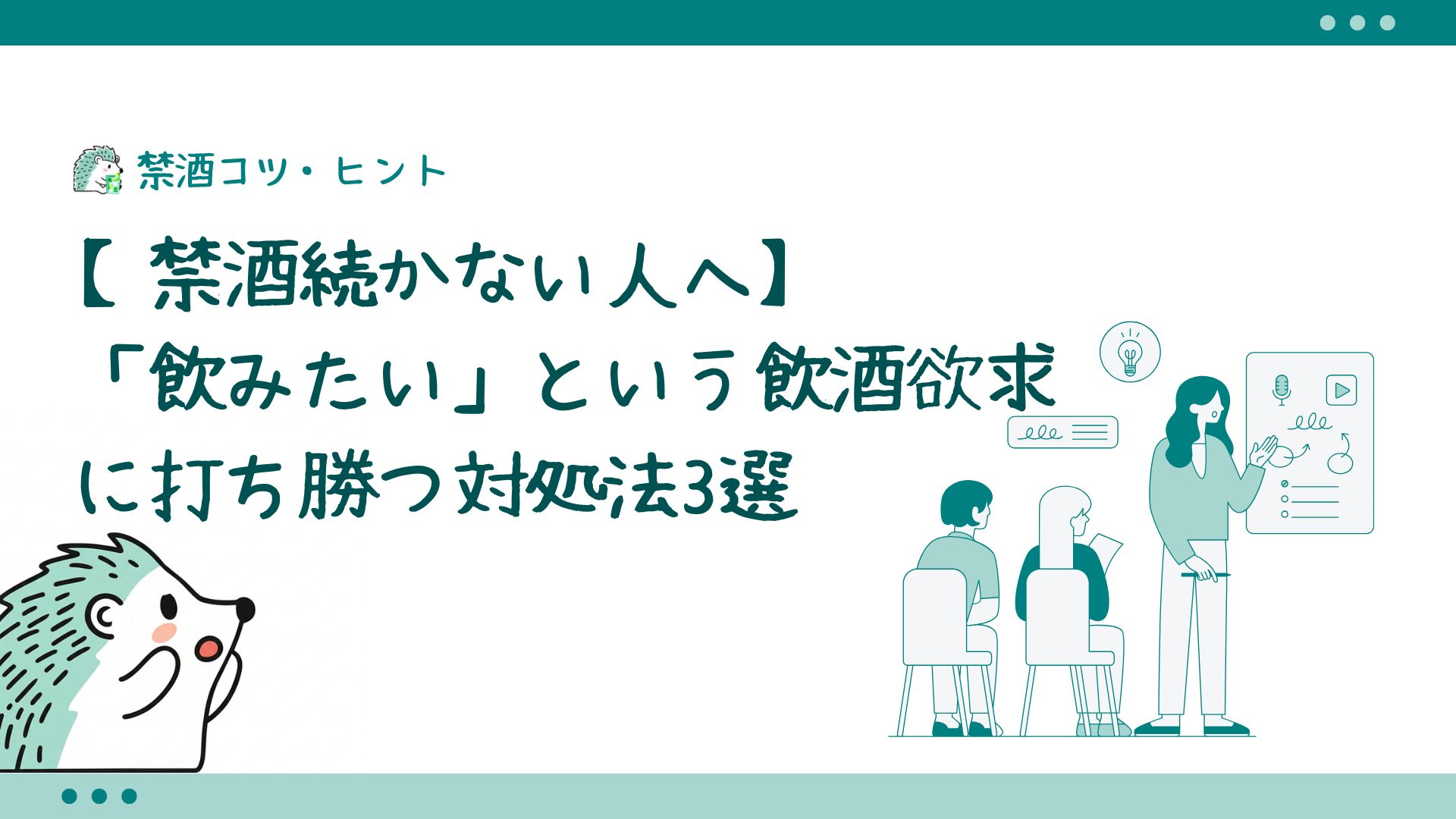

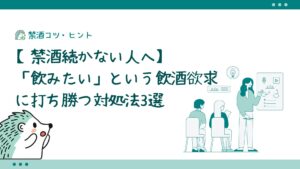

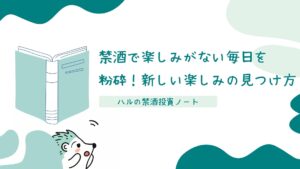
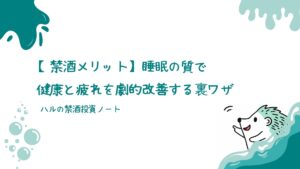
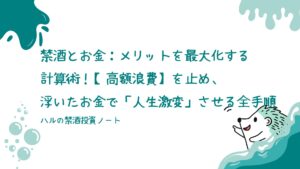
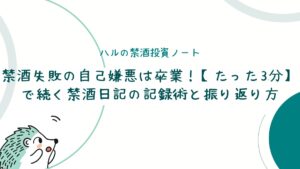
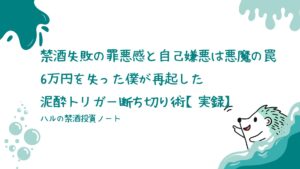
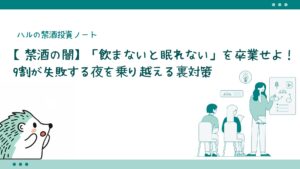
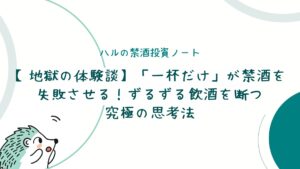
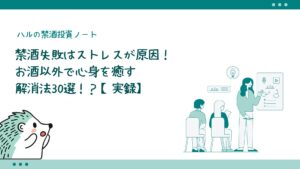
コメント