禁酒を続けていると、やる気がなくなることってありませんか?僕も、禁酒をしているときによく何で禁酒してるんだろう?別に飲んでも良くない?意味ないしと、ふとした瞬間に思って、禁酒を続けるモチベーションがさがることがあります。
- 禁酒を始めて、早くも心が揺らいでいる人
- お酒を我慢することに意味を見出せなくなってきた人
- 禁酒のモチベーションを維持する方法が知りたい人
 ハル
ハル今回は、そんな僕が禁酒生活で直面した心の葛藤と、それを乗り越えた方法を心理学的な視点も含めて正直にお話します。この記事を読めば、心が軽くなり、誰もが通るモチベーションの壁を乗り越えるためのヒントが見つかるはずです。
結論:モチベーション維持のための5つの心理学的アプローチ
禁酒中のやる気のなさを乗り越えるには、心理学的アプローチを実践することが有効です。僕がこの壁を乗り越えるためにやったことは、次の5つです。
実行意図:「未来の自分」から「今日の自分」へ目標を変える
漠然とした目標を「もし〜なら、〜する」という具体的な行動に落とし込み、やる気に頼らない仕組みを作る。
自己効力感:小さな成功体験を積み重ね、自信に変える
小さな成功体験を積み重ねることで、「自分にもできる」という自信を育み、モチベーションの土台を築く。
目標設定理論:「記録」で頑張りを可視化する
記録によって頑張りを可視化し、達成感を味わうことで、継続への意欲を高める。
習慣の置き換え:「飲酒」を「別の習慣」に置き換える
飲酒欲求を「我慢」するのではなく、別の行動に切り替えることで、飲酒がもたらしていた「報酬」を新しい習慣から得る。
自己同情「お酒を飲んだらダメだ」という考え方を捨てる
失敗しても自分を責めず、自分に優しく接することで、挫折から立ち直る力をつけ、長期的なモチベーションを維持する。



この記事では、僕がこの5つの方法をどのように実践したのかを、ひとつずつ具体的に解説していきます。読み終える頃には、あなたの心が少し軽くなり、禁酒を続けるためのヒントが見つかるはずです。
【解決策1】実行意図:「未来の自分」から「今日の自分」へ目標を変える
禁酒を始めて、時間が経つにつれて、始めた時の決意が薄れていくのを感じました。漠然とした「より良い未来」を想像するだけでは、目の前の飲酒欲求に勝てない。
長期的な目標は、具体的ではなく、どこか遠い存在に感じられて、モチベーションを維持するのは難しいのです。
そこで僕は、今日だけ我慢しよう。お酒が飲みたくなったら、ノンアルコールのビールを飲むようにしようとチョキ的な漠然な目標を短期的で具体的な目標に変更しました。
すると、漠然として具体的なことが想像できない長期的な目標と違い、行動に移すのが思いのほか楽になり、禁酒を続けていくことができました。
この考え方は、心理学者のペーター・ゴルヴィツァーが1980年代に提案した、習慣化のためのテクニック(実行意図)です。
「もしXが起きたら、Yをする」というように、目標達成を妨げる特定の状況(X)と、それに対する具体的な行動(Y)を事前に決めておくことで、自動的に行動を起こしやすくなると言われています。
これは、漠然とした目標(例:「禁酒する」)を、具体的な行動(例:「今日、飲みたくなったらノンアルコールビールを飲む」)に落とし込むことで、やる気に頼らずとも目標を達成しやすくするという考え方に基づいています。
【解決策2】自己効力感:小さな成功体験を積み重ね、自信に変える
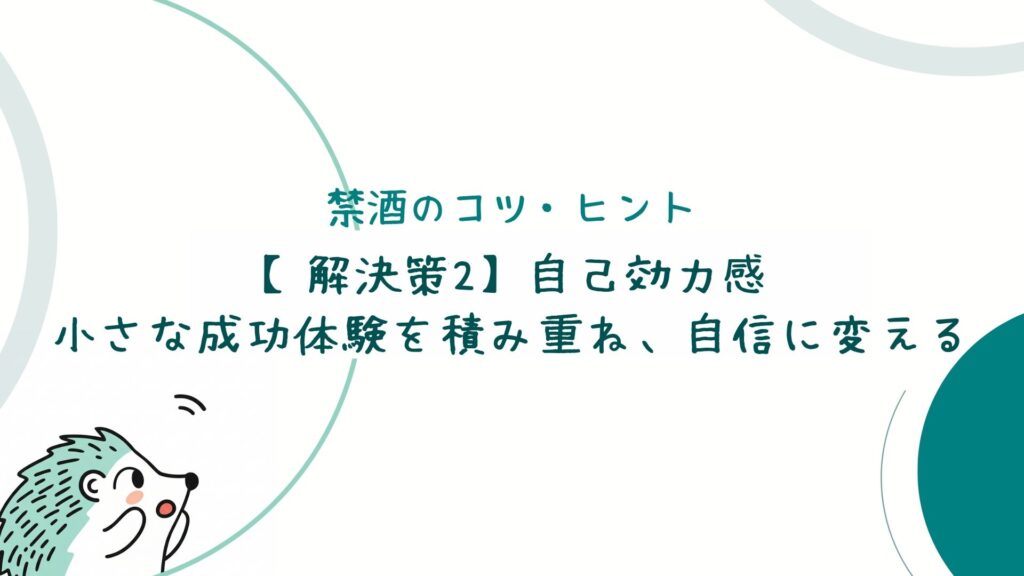
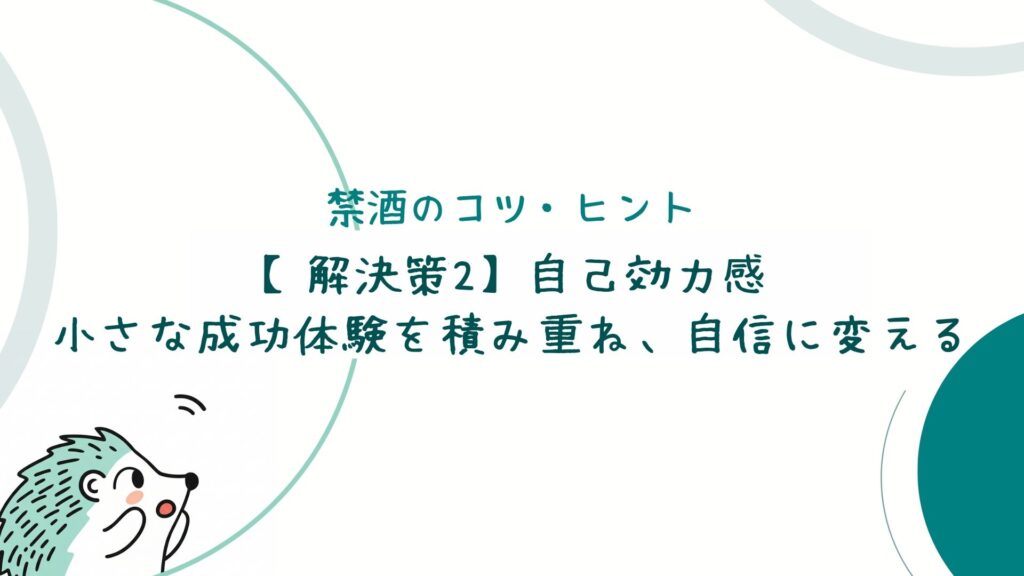
禁酒を始めた時に、僕は毎日ブログを更新したり、ツイッターで禁酒していることを発信したりすることを目標にしました。
お酒を飲まないという、他人から見れば些細なことでも、僕にとっては死ぬほどつらいことでした。でも、この「つらいこと」を乗り越えること、そして毎日ツイートするという小さな目標を継続することが、自分にとっての成功体験となり、少しずつ自信に繋がっているのを感じました。
この感覚は、心理学者のアルバート・バンデューラが提唱した「自己効力感(Self-Efficacy)」という概念で説明できます。
自己効力感とは、「自分には目標を達成できる能力がある」と信じる心の状態を指します。禁酒を達成できたという小さな成功は、この自己効力感を高めます。
つまり、「昨日できたから、今日もできるはずだ」という感覚が生まれ、それがモチベーションの維持を助けるのです。
【解決策3】目標設定理論:「記録」で頑張りを可視化する
禁酒の記録は、孤独な戦いではありません。僕はブログやSNSに記録することで、自分の頑張りを目に見える形にしました。
「禁酒2日目!なんとか乗り越えました」「今日も禁酒成功!」といった記録をつけるたび、達成感が得られ、それが次の日のやる気に繋がっていきました。
また、ツイッターで禁酒の進捗を発信し始めたとき、「誰かに見られている」という感覚が生まれ、それがお酒を飲みたいと思ったときに踏みとどまる、大きな力になってくれました。
心理学者のエドウィン・ロックが提唱した「目標設定理論」では、目標を漠然としたものではなく、具体的で明確に設定することで、人のパフォーマンスが向上するとされています。
この理論の主な要素は以下の3つです。
- 具体性: 「禁酒をする」ではなく、「今月は金曜日だけ禁酒する」のように、目標を明確にします。
- 困難性: 簡単すぎず、難しすぎない、少し頑張れば達成できる目標を設定します。
- フィードバック: 目標に対する進捗を定期的に確認し、評価します。
僕が「禁酒2日目!」と記録をつけたのは、これらの要素すべてに関わっています。「2日目」という具体的な目標を、少し頑張って達成し、「記録」することで進捗を評価したからです。
目標を公の場で宣言し、記録を公開することは、「パブリック・コミットメント効果」として知られています。
この概念は、社会心理学者のロバート・B・チャルディーニの著書『影響力の武器』などで有名です。人は、他者に対して宣言したことを守ろうとする心理が働くため、挫折しにくくなります。
僕がツイッターに禁酒の進捗を発信したことで、お酒を飲みたいときに踏みとどまれたのは、この効果が働いたからです。
【解決策4】習慣のループ:「飲酒」を「別の習慣」に置き換える
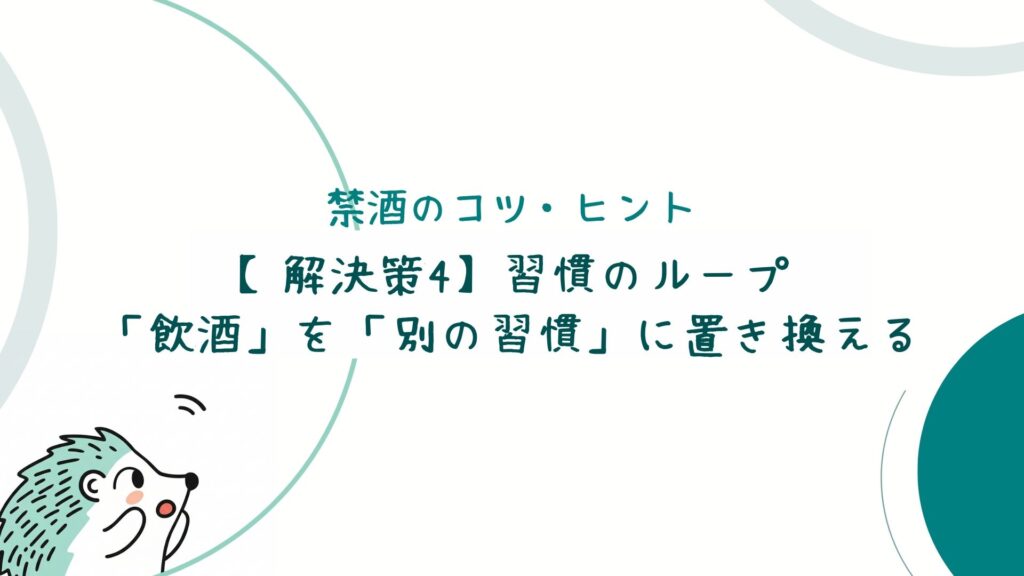
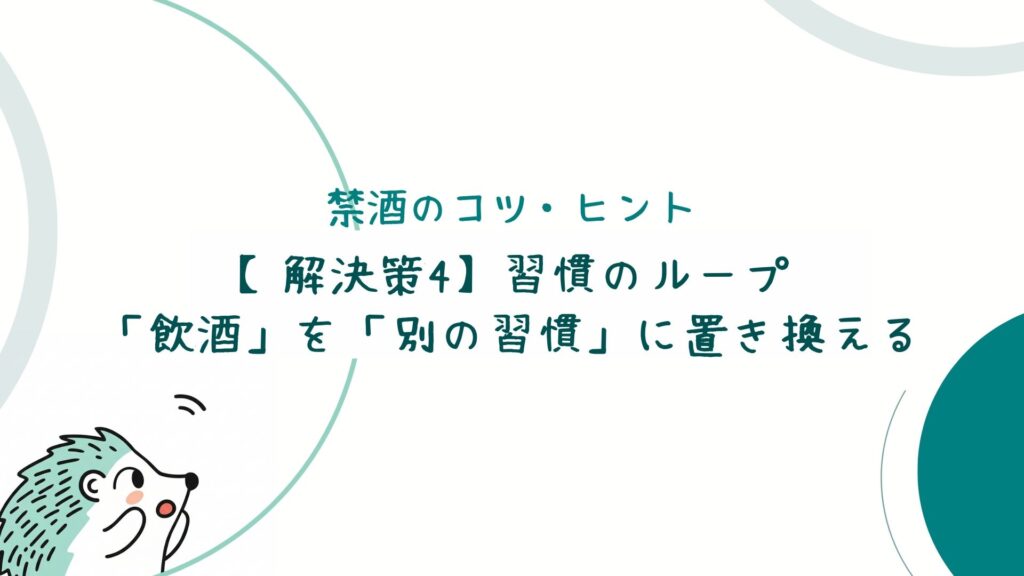
飲酒欲求を「我慢」するのではなく、「別の行動」に置き換えることを試みました。僕の場合、ノンアルコール飲料を常備したり、オンラインゲームに没頭したりしました。
特に、ゲームに没頭している間は、飲酒欲求のことをすっかり忘れることができました。
ジャーナリストのチャールズ・デュヒッグが著書『習慣の力』で提唱した「習慣のループ」という概念があります。
これは、以下の3つの要素で形成されます。
- きっかけ: 脳に「特定の習慣を開始せよ」と伝える引き金(例:仕事終わり)。
- ルーティン: 物理的、精神的、感情的な行動そのもの(例:お酒を飲む)。
- 報酬: 脳がそのルーティンを将来も覚えておくための快感(例:リラックス)。
禁酒で挫折しがちなのは、このループが断ち切られるからです。
これを乗り越えるには、「お酒を飲む」というルーティンを、「ノンアルコール飲料を飲む」「ゲームに没頭する」といった別の行動に置き換え、同じ報酬(リラックスや達成感)を得ることが効果的です。
僕がゲームに没頭したことで飲酒欲求を忘れたのは、「お酒を飲む」というルーティンを「ゲームに没頭する」という新しいルーティンに置き換えることで、同じ報酬(気分転換や達成感)を得ることができたからです。
【解決策5】自己同情:「お酒を飲んだらダメだ」という考え方を捨てる
僕は、禁酒を始めたばかりの頃、「絶対に飲んではいけない」という強い縛りを自分に課していました。
その結果、少しでも飲んでしまうと、「もうダメだ…」「禁酒は失敗だ」と自己嫌悪に陥り、かえって投げやりになってしまうことが多々ありました。
そこで、僕は考え方を変えることにしました。「完璧主義」を捨て、「今日はたまたま飲んでしまったけど、明日からまた頑張ろう」と、自分に優しく接することにしました。
この考え方を変えたことで、気持ちが楽になり、長期的な禁酒に繋がりました。
この極端な思考は、認知行動療法(CBT)という心理療法の分野で広く知られる「認知の歪み」の一つです。
これを体系化した心理学者、アーロン・ベックは、「少しでも失敗したらすべてが無駄になる」という思考が、わずかなミスで自己嫌悪を引き起こし、モチベーションを完全に失わせてしまうと指摘しています。
僕が「禁酒は失敗だ」と自己嫌悪に陥っていたのは、この思考に陥っていたからです。
心理学者のクリスティン・ネフ(Kristin Neff)は、失敗した自分を厳しく責めるのではなく、「自己同情」をもって優しく接することの重要性を提唱しています。
失敗した時でも「人間だから失敗はするよね」「明日からまた頑張ろう」と受け入れることで、挫折から素早く立ち直り、長期的な目標達成に繋がります。
自己同情は、単に甘やかすことではありません。自分に優しくすることで、ネガティブな感情を健全に処理できるようになり、失敗から学び、自己成長を促進する効果があります。
僕が「今日はたまたま飲んでしまったけど、明日からまた頑張ろう」と自分に優しく接することで、気持ちが楽になり、長期的な禁酒に繋がったのは、この自己同情が働いたからです。
結論:モチベーション維持のための5つの心理学的アプローチ
この記事では、禁酒における「やる気のなさ」を乗り越えるための5つの心理学的アプローチを、僕自身の経験を交えてご紹介しました。
- 実行意図: 「未来の自分」ではなく、「今日の自分」に焦点を当てる
- 自己効力感: 小さな成功を積み重ね、自信を育む
- 記録の可視化: 頑張りをオープンにし、外部からの力を借りる
- 習慣の置き換え: 飲酒を「別の行動」に切り替える
- 自己同情: 失敗を責めず、自分に優しく接する
完璧を目指す必要はありません。今日から一つずつ試してみて、「これならできそう」と思えるものからぜひ始めてみてください。
禁酒で得られるメリット・効果
禁酒を始めたばかりの頃は、正直メリットがよく分からないかもしれません。でも、禁酒を続けると、僕たちが思っている以上に様々な良い変化が起こります。
- お金:出費が減って、将来のための貯金や投資ができる
- 時間:二日酔いや無駄な時間がなくなり、自由に使える時間が増える
- 健康:体の内側から調子が良くなり、ダイエットや美容にもつながる
- メンタル:自己肯定感が高まり、自分に自信がつく
- 人間関係:お酒に頼らない、本当の信頼関係を築ける
僕が実際に感じた「禁酒で得られるメリット」について、詳しくまとめた記事がありますので、ぜひ読んでみてください。
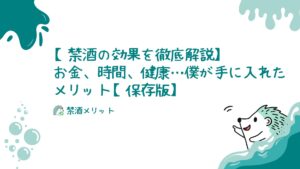
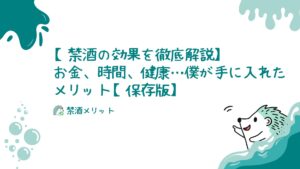
禁酒中のおともには、サントリーオールフリーがおすすめ!!
サントリーオールフリーは、禁酒中の僕にとって、十分すぎるほど満足できる最高の相棒でした。
もちろん、本物のビールとは違うと感じる部分もあります。でも、ノンアルコールでありながらビールの風味を再現していて、我慢ばかりの禁酒生活から僕を救ってくれたのは間違いありません。
特に、「プリン体ゼロ」「カロリーゼロ」「糖質ゼロ」という点も、健康を意識している僕たちには嬉しいポイントです。
サントリーオールフリーのレビュー記事も書いてます。禁酒中にどうしても飲みたくなることもあると思いますが、そんな時はぜひ、サントリーオールフリーを試してみてください!
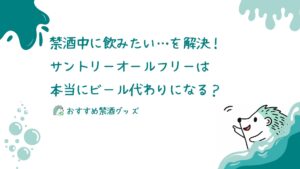
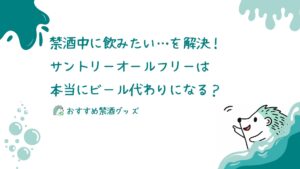
まとめ:禁酒は「我慢」ではなく「自分を大切にすること」
禁酒は「お酒を我慢するつらい戦い」ではありません。
これまで見てきたように、心理学の知識を借りて行動や考え方を変えれば、きっと誰でも達成できる目標です。最も大切なのは、「自分を責めず、優しく向き合うこと」です。
この記事でご紹介した5つの解決策のうち、たった一つだけでも構いません。「これならできそうだ」と感じたものから、ぜひ試してみてください。



僕もまだまだ道半ばです。でも、もしこの記事があなたの小さな一歩のきっかけになれたなら、とても嬉しいです。
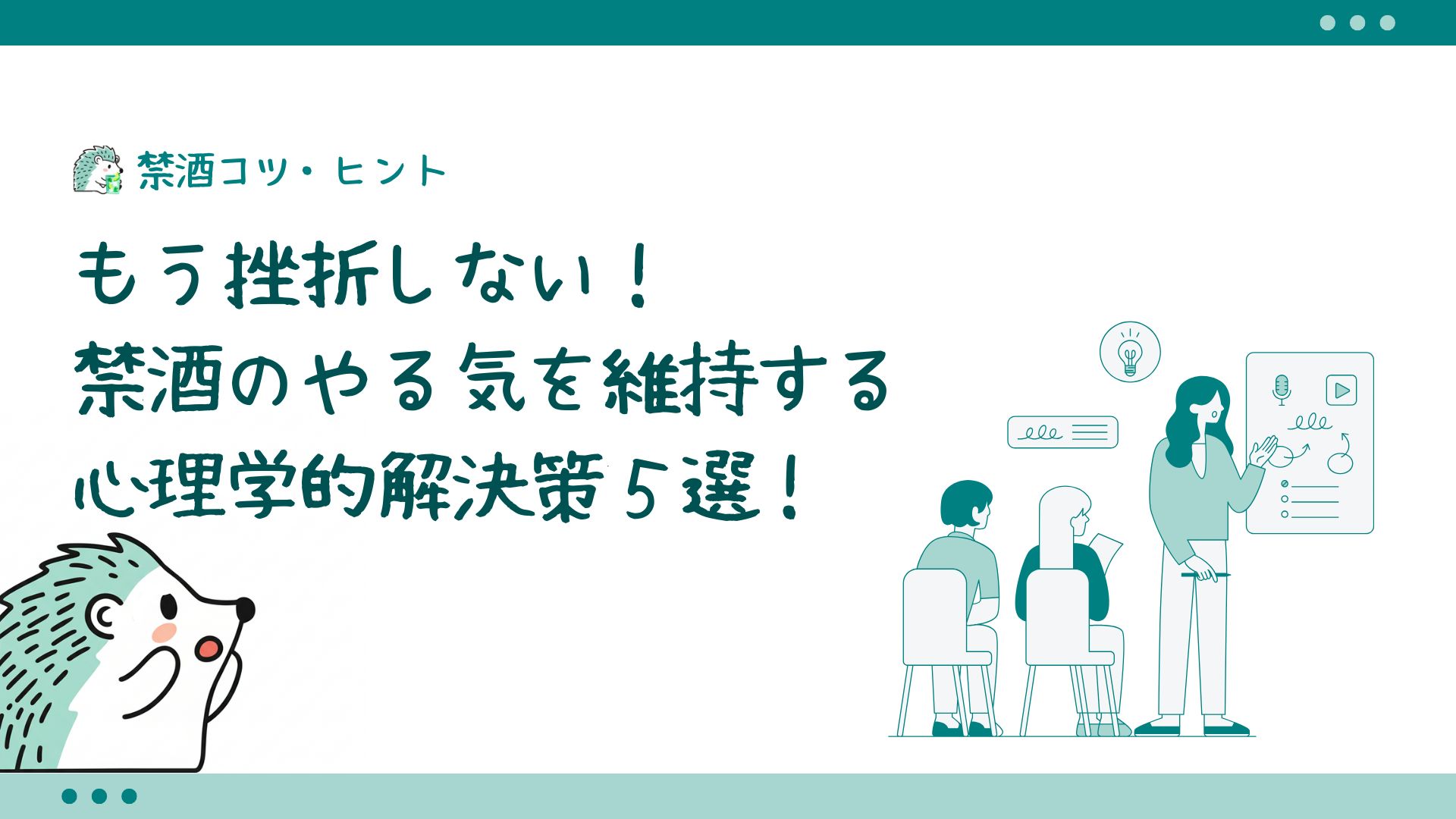

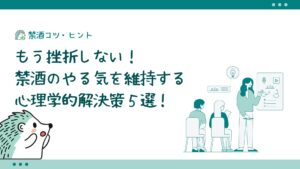

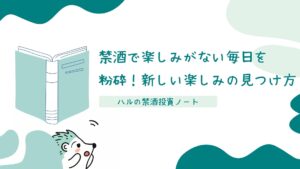
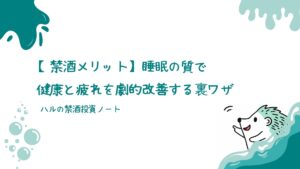
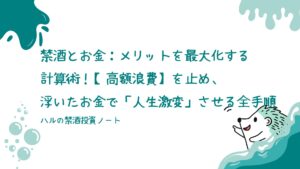
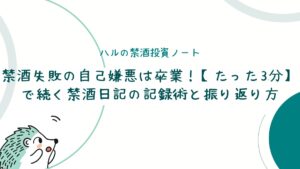
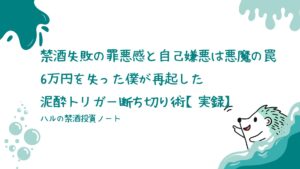
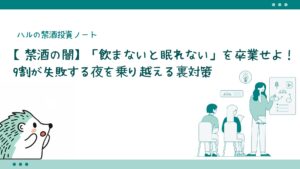
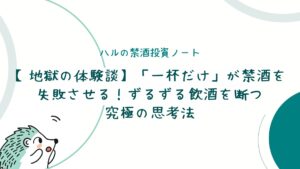
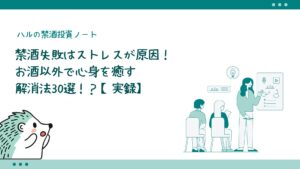
コメント