禁酒のだるさを解消する鍵は「原因の特定」と「時間帯」にあります。
禁酒中のだるさは本当に辛いですよね。
「ベッドから出たくない」「仕事が手につかない」
僕もその気持ち、痛いほどわかります。特に、介護職で体力が必要な僕にとって、だるさは仕事の質に直結する死活問題でした。一番知りたいのは、「今すぐ楽になる方法」だと思います。
この記事は、だるさの原因(脳の興奮と栄養不足)に基づいた、即効性のある解消法を時間軸でまとめました。
- だるさのタイプ別に、今すぐ(5分以内)できる対処法がわかる。
- 30分以内に体を回復モードに切り替える具体的な栄養補給法がわかる。
- 僕が最長22日間禁酒を継続できた「だるさへのマインドセット」がわかる。
 ハル
ハルだるさは、体が回復を求めているサインです。正しい方法で、この辛い時期を乗り越えましょう!
5分でできる即効リセット法|「脳の興奮」を落ち着かせる
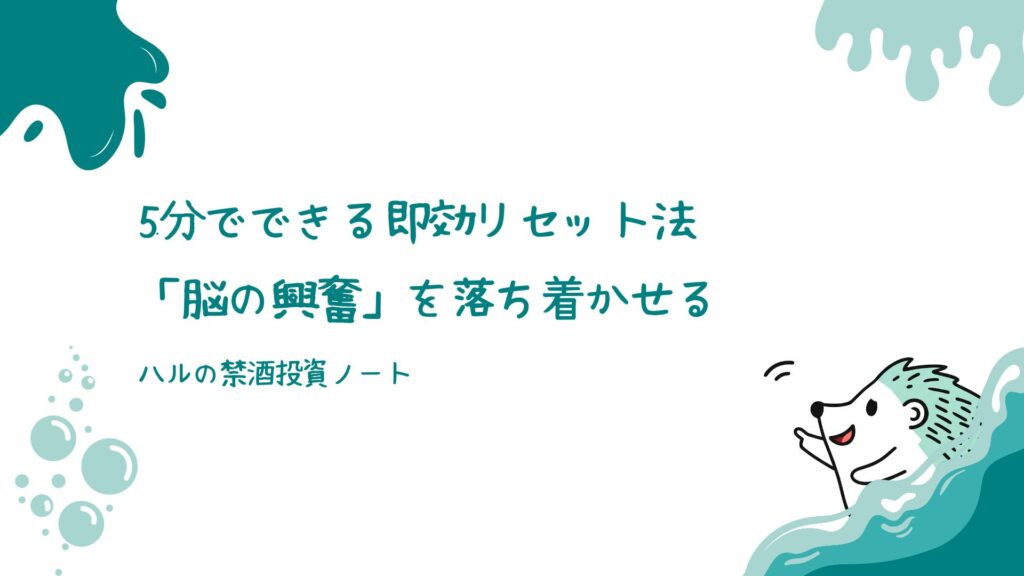
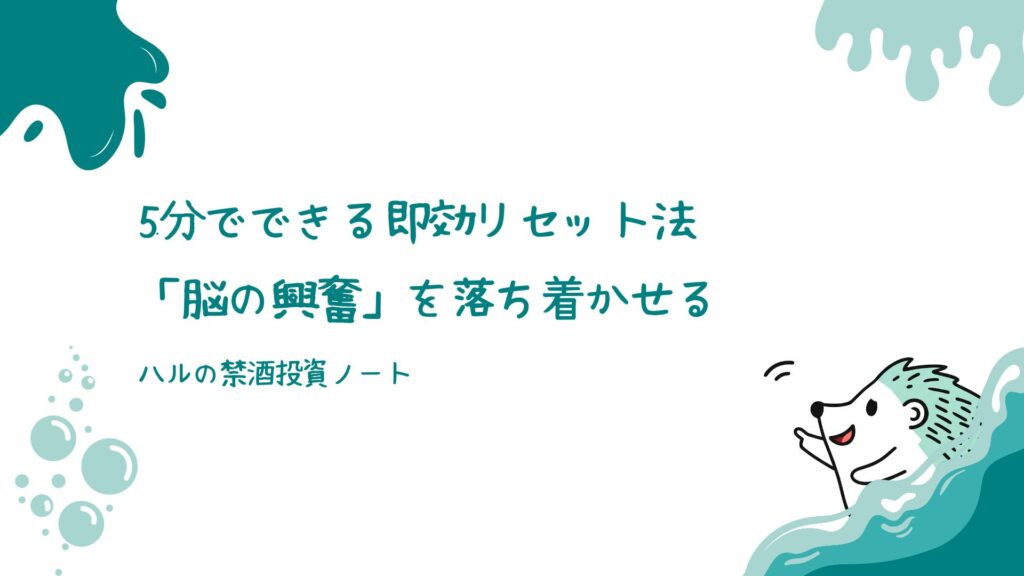
この方法は、主に離脱症状による「イライラや焦燥感を伴うだるさ」を感じているときに効果的です。原因である自律神経の乱れと脳の興奮を、今すぐ落ち着かせる方法です。
僕が実際に試した方法は以下の3つです。
- 脳の興奮を鎮める「4-7-8呼吸法」
- Vagus Nerve(迷走神経)を刺激する「冷たい水」
- 飲酒欲求を逸らす「失敗の再認識とSNS」
脳の興奮を鎮める「4-7-8呼吸法」
| 解決法 | 具体的な行動 | メカニズム(なぜ効くか) |
|---|---|---|
| 深呼吸 | 4秒吸う→7秒止める→8秒かけて吐く。これを5回繰り返す。 | 意図的に呼吸をコントロールすることで、興奮した自律神経(交感神経)を落ち着かせる効果があると言われています。 |
周りの職員のお喋りや車の音などの音でイライラしたとき、僕は席を外してこれをやりました。交感神経が優位になっている状態(脳のパニック)を意識的に鎮めることが重要だと感じました。
Vagus Nerve(迷走神経)を刺激する「冷たい水」
| 解決法 | 具体的な行動 | メカニズム(なぜ効くか) |
|---|---|---|
| 冷水刺激 | 冷たい水を少量口に含む、または顔や首の後ろに当てて冷やす。 | 迷走神経が刺激され、心拍数が下がり、鎮静作用をもたらすことが知られています。これは、離脱症状による興奮を和らげると考えられています。 |
飲酒欲求を逸らす「失敗の再認識とSNS」
- 行動: 強烈な飲酒欲求が襲ってきたとき、禁酒の失敗(路上泥酔、財布紛失、5万浪費など)を思い出し、SNSで禁酒仲間の投稿や「いいね!」の数を確認する。
- 効果: 僕は飲酒のネガティブな結果を思い出すことで、一瞬で現実に引き戻され、飲酒欲求を逸らしました。また、同じように頑張る仲間の存在は、「自分は一人じゃない」という安心感につながり、即効性のある心の支えになりました。
僕は禁酒生活を始めて2か月ほどたちました。禁酒の失敗は数えきれません。でも、その度に立ち直り、最長22日連続禁酒を達成することもできました。毎回へこんでますが、諦めて辞めてしまっては全てが水の泡です。
禁酒は継続が命。失敗して反省し、対策することが重要です。僕のリアルな失敗談から、どうやって気持ちを立て直し、再スタートを切ったのか、そのヒントを全て、【禁酒失敗談】もうダメだと諦めない!立ち直り方と再スタートのヒント【実録】で公開しています。
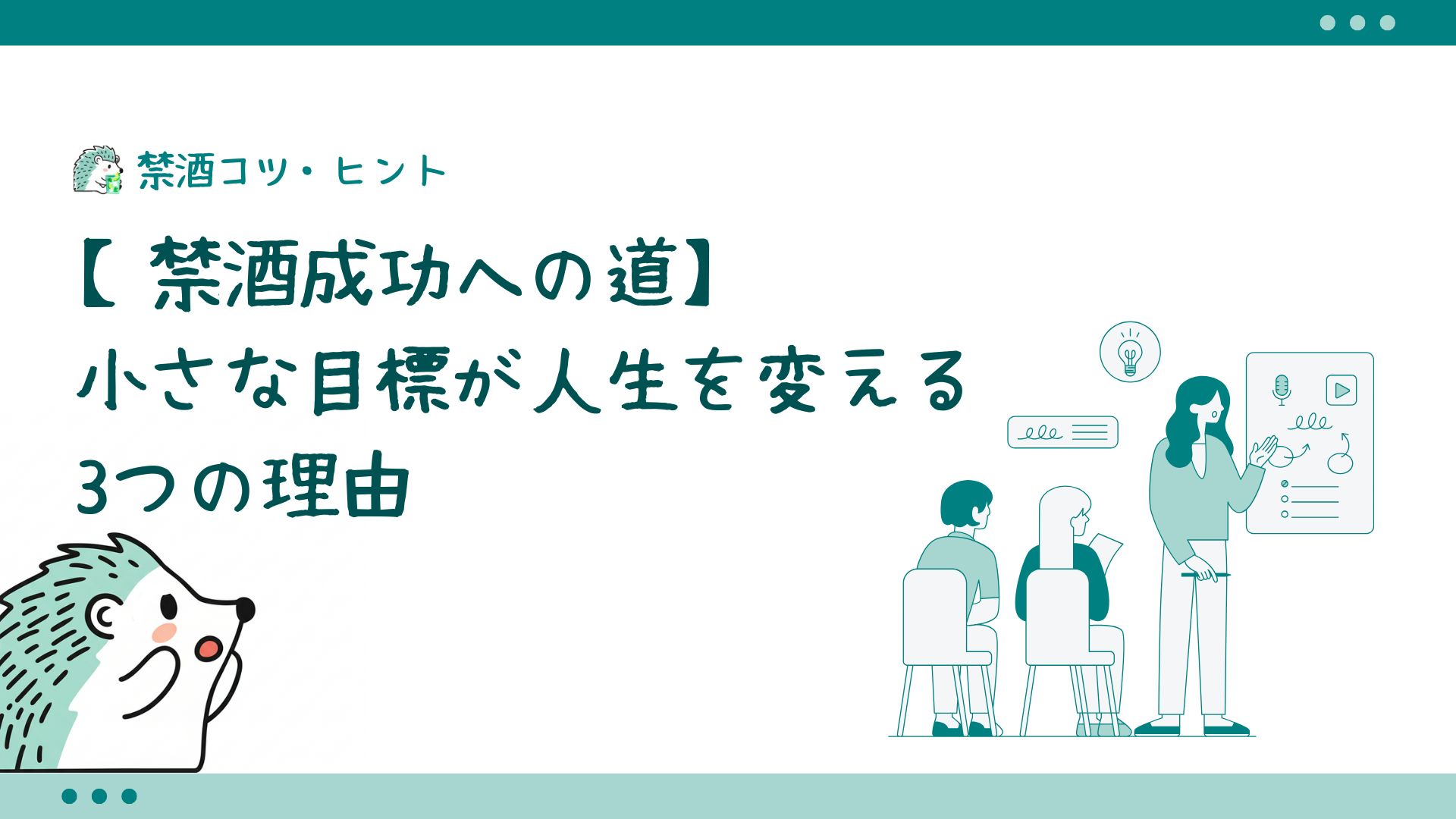
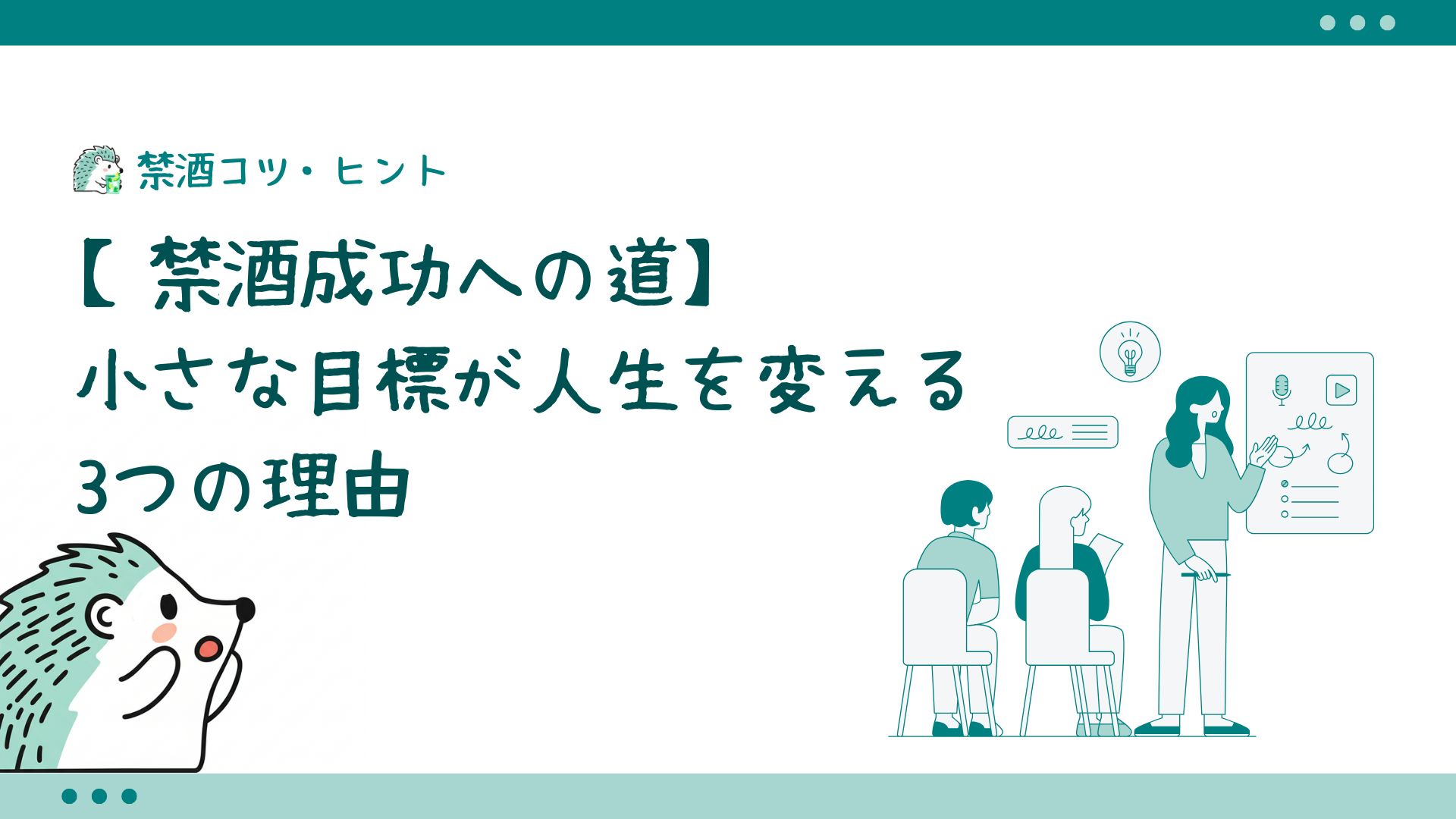
僕自身、禁酒に挑戦して2ヶ月間続けているんですが、SNSで記録をつけるようにしてから、飲酒欲求に勝てる気がしています。
最初は投稿するのが恥ずかしくて、2ヶ月間アカウントだけ作って何も発信できていませんでした。
でも、いざ始めてみると、同じように禁酒を頑張っている人が結構いて、投稿に「いいね!」をつけてくれたりするんですよ。
これが「一人じゃないんだな」と感じられて、すごい励みになっています。
自分の頑張りが可視化されるから、モチベーション維持にも繋がっています。失敗が多い僕でも、やらないよりはやった方が絶対に飲酒欲求に勝てる回数が増えると思っています。
SNSで禁酒記録をつけることで、必ず飲酒欲求を抑える手助けとなります。SNSでの禁酒記録については、【禁酒が続かない人へ】挫折寸前だった僕がSNSで禁酒を続けられた理由【実録】で詳しく解説しています。
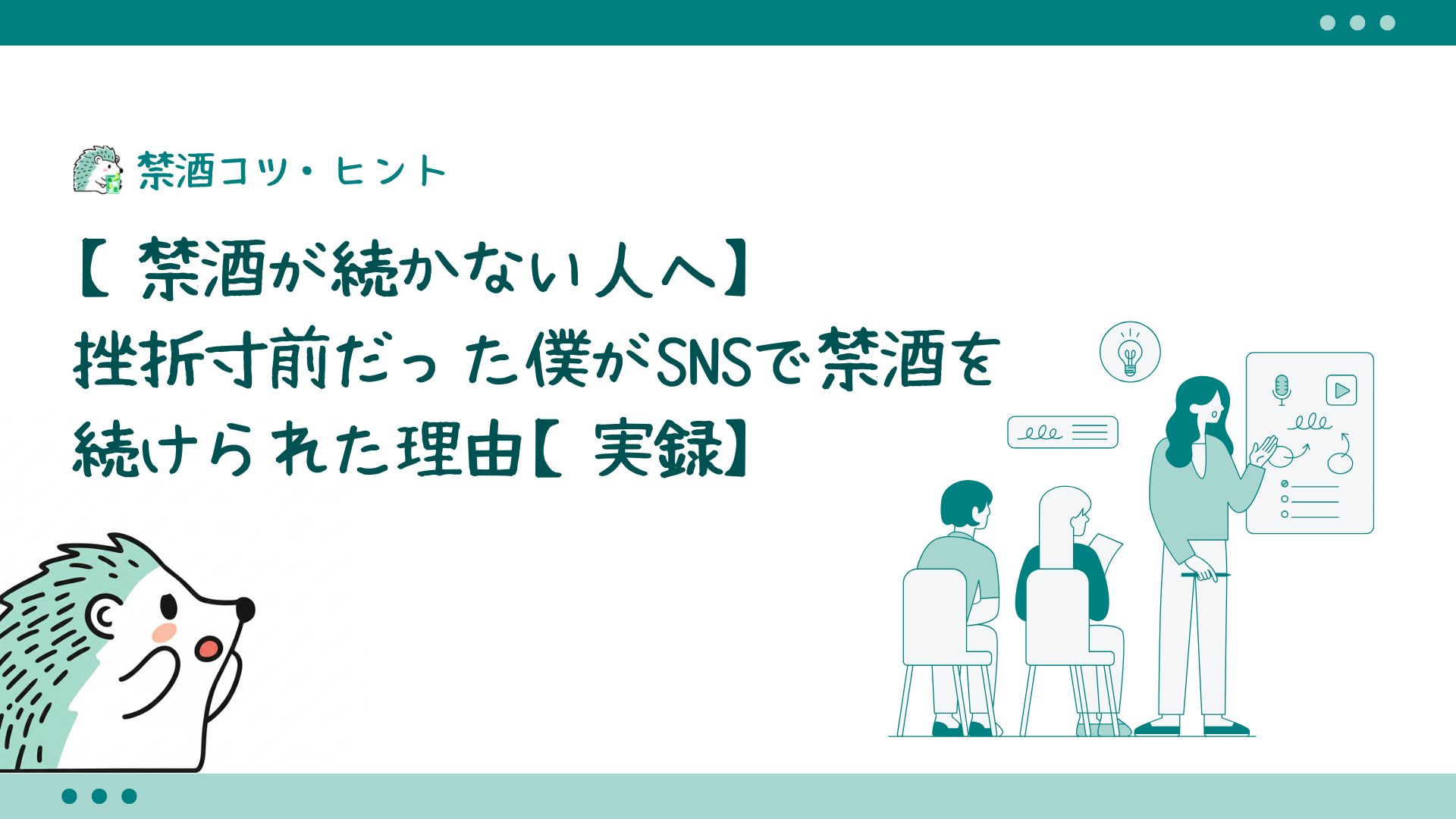
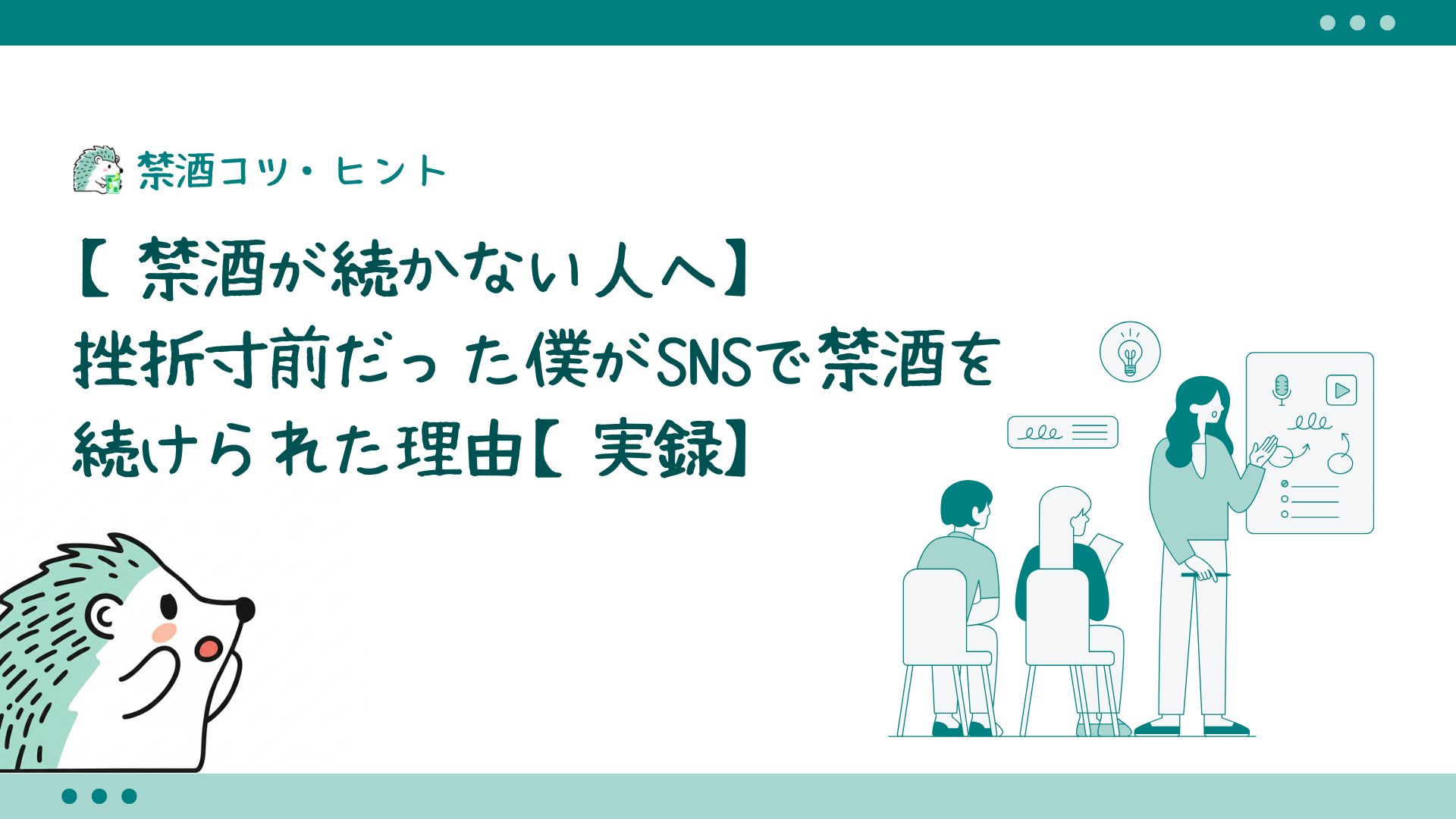



イライラや焦燥感が強いときは、まず深呼吸と冷水で、興奮した脳を「強制的に落ち着かせる」ことが最優先です。
30分で回復を加速する栄養法|「エネルギー不足」を補う
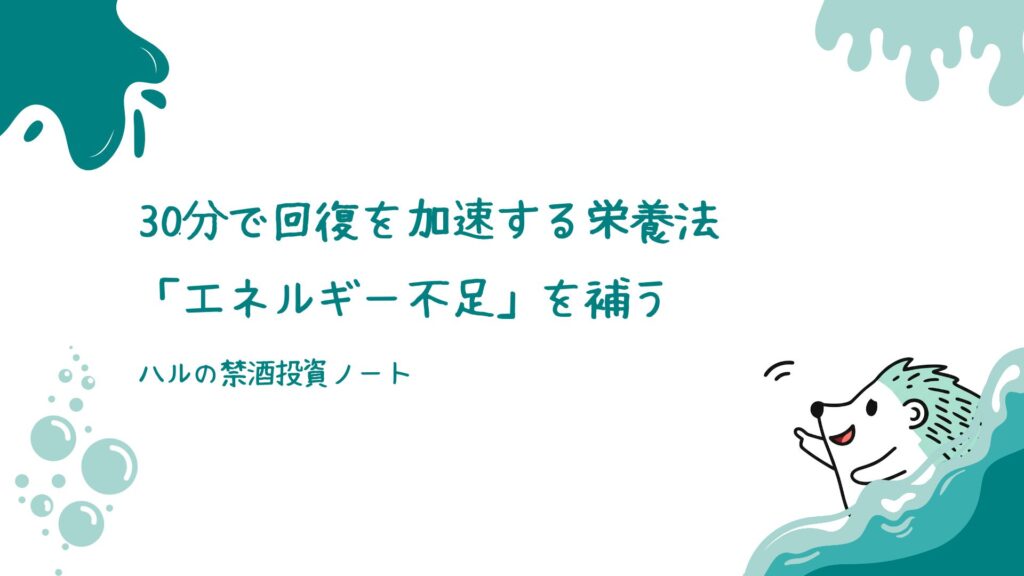
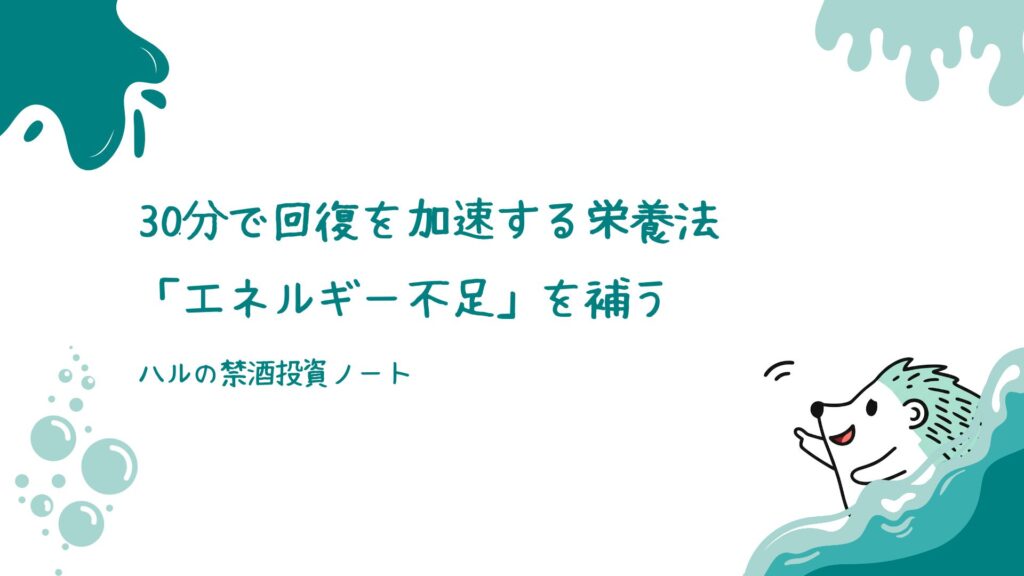
この方法は、主に栄養不足による「鈍重な無気力」が続いているときに効果的です。エネルギー生成に必要な栄養素を迅速に補給し、肝臓の修復をサポートします。
1.禁酒中の最重要栄養素「ビタミンB1」のクイック補給
- 解決法:B1クイック補給
- 具体的な行動:納豆を1パック食べる、または豚肉(モモ/ヒレ)が入った軽食を摂る。
- メカニズム:ビタミンB1は糖質をエネルギーに変える鍵であり、不足すると倦怠感が起こるとされています。僕も納豆を毎日摂り始めてから集中力が劇的に回復しました。
- 豚肉(特にヒレ肉やモモ肉)
- うなぎ
- たらこ
- 玄米・胚芽米
- 大豆製品(納豆など)
納豆と豚肉を毎日摂るようになって10日目くらいから、イライラが緩和されたと感じています。以前は職場の雑談が気になっていましたが、それが収まり、作業に没頭できるようになりました。
ブログ記事の作成で5時間も集中力が持続できるようになったのは、栄養補給の成果だと感じています。
2.肝臓の修復を助ける「クエン酸とアミノ酸」
| 解決法 | 具体的な行動 | メカニズム(なぜ効くか) |
|---|---|---|
| アミノ酸補給 | クエン酸(レモン水など)やオルニチン(しじみの味噌汁など)を摂る。 | 肝臓の修復作業には大量のエネルギーが必要です。これらは疲労回復を助け、肝臓の負担を軽くするサポート役として役立つと言われています |
禁酒のだるさ対策で大切なのは、離脱症状、栄養不足のどちらが原因かを見分けて、それぞれにあった対処法をとることです。僕は、食事を変えることで、栄養不足を改善し、集中力が上がって、ブログを毎日1記事あげられるまでになりました。
離脱症状、栄養不足のだるさの見分け方については、禁酒のだるさ、「離脱症状」と「栄養不足」どう見分ける?【介護職の僕が体験したサインの境界線】で解説しています。
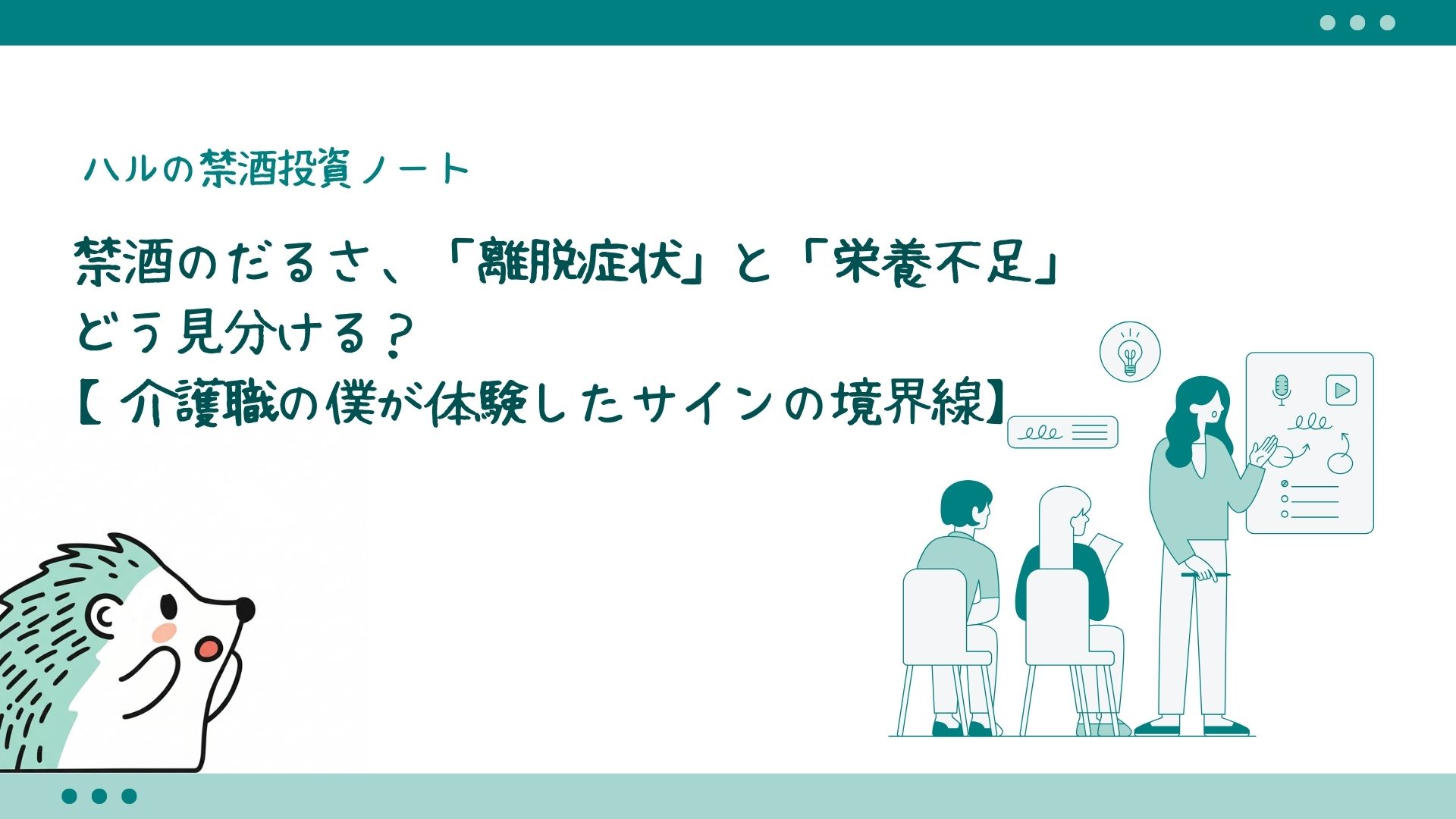
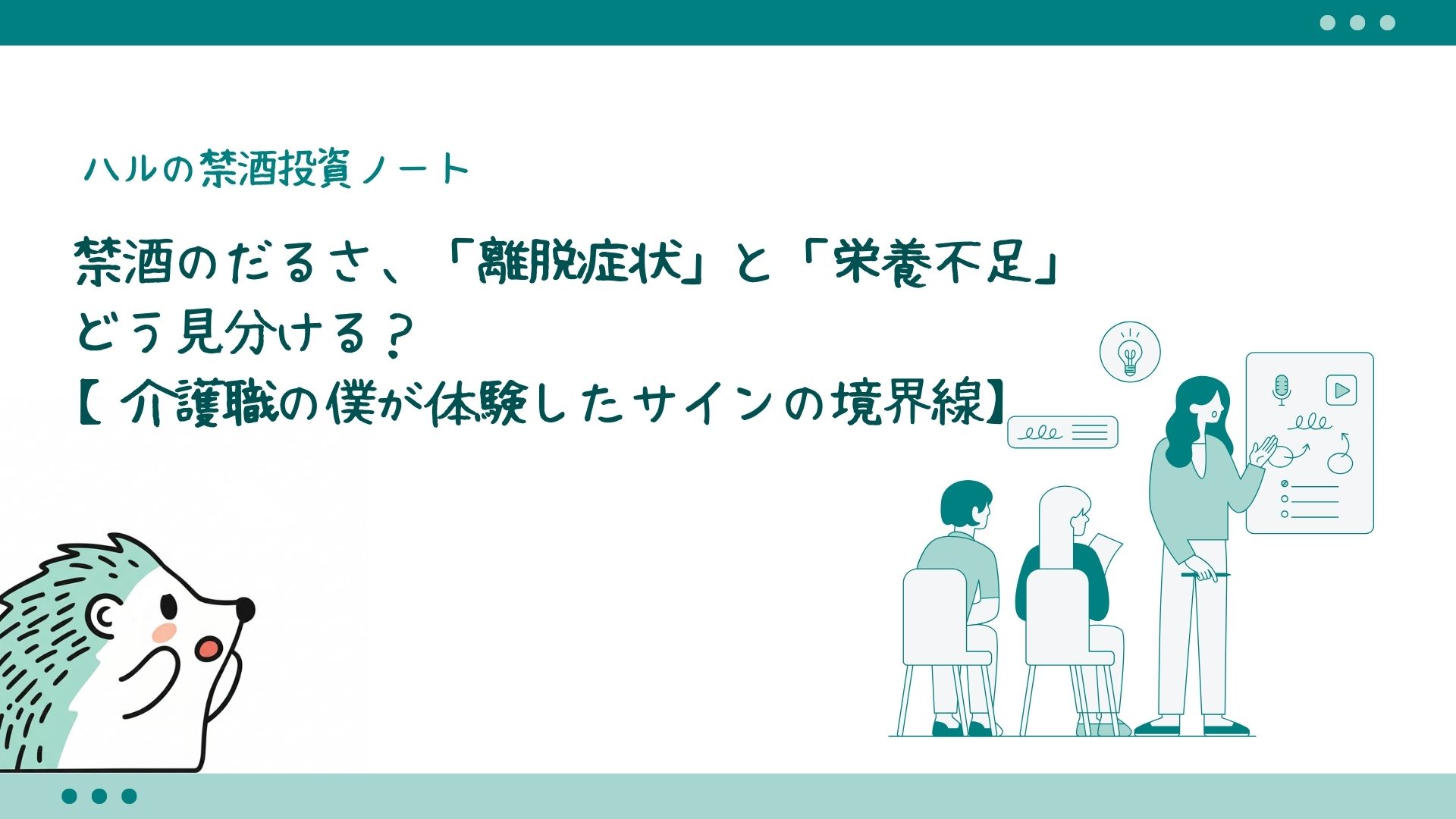



無気力や倦怠感が続くなら、休息だけでなく、納豆や豚肉でエネルギーの「種(B1)」を急いで補給しましょう。
今日一日を乗り切るための「心の即効薬」
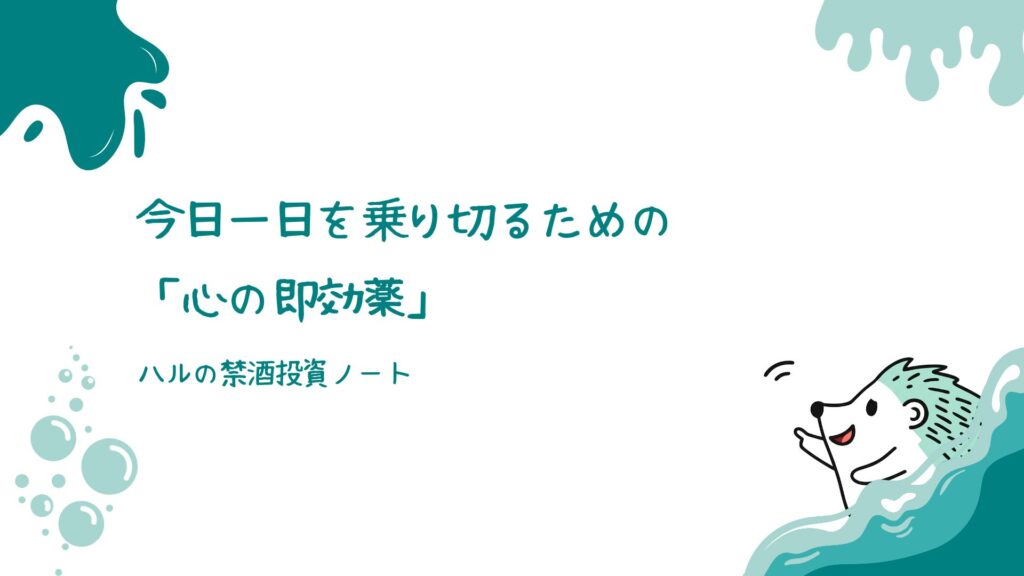
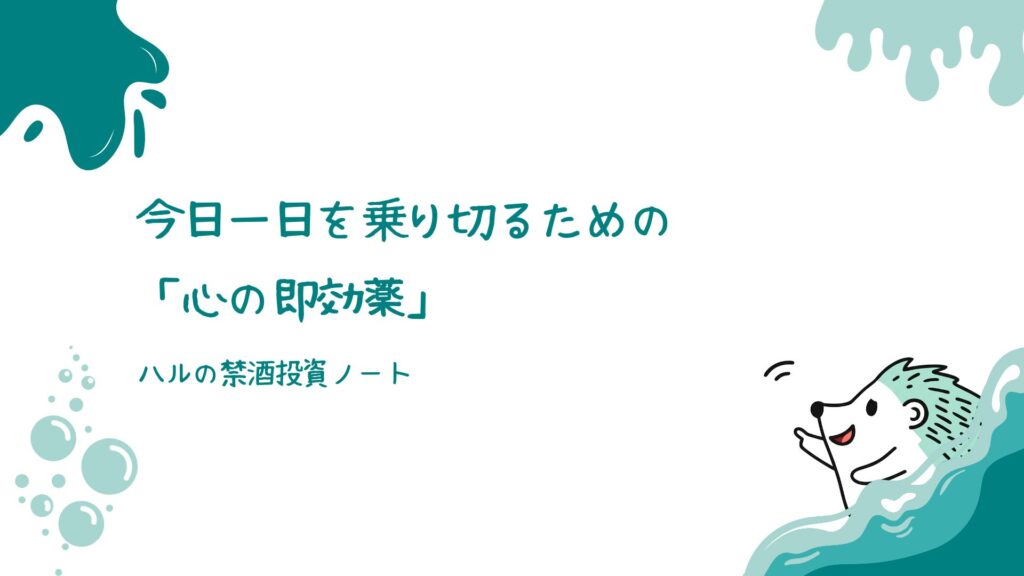
だるさの解消法は、身体的なアプローチだけでなく、精神的な切り替えも重要です。僕が禁酒初期に辛い時期を乗り越えるために使った「心の即効薬」を紹介します。
1.「好転作用」のマインドセットを思い出す
- 行動: だるさを感じたら、「体が良くなろうとしているサインだ」「今デトックス中だ」と口に出して言う。
- 効果: 僕は「辛ければ辛いほど、大きく成長できるんじゃね?」という考え方に変えたことで、辛さが乗り越えるべき壁に変わりました。このマインドセットは、体のだるさがピークの時に最も効果を発揮する心の即効薬です。
2.「仕方ない」ルールを適用する
- 行動: 集中力が切れたり、ミスをしたりしても、自分を責めない。「仕方ない、次に行かそう」と自分に優しく語りかける。
- 僕の体験談(仕事での効果):介護の仕事中、理不尽な理由で利用者さんに怒られたことがありましたが、聞き流しながら冷静に対応できました。これは、「仕方ない、次に活かそう」というマインドセットが役立った瞬間です。失敗した時も、以前のように「まじかわんねーな」と自分を責める時間が減り、「次に行かそう」と切り替えられるようになりました。



だるさは「体のSOS」であると同時に、「成長の準備」です。自分を責めず、前向きな言葉で乗り切りましょう。
まとめ
まずは5分で試せる改善方法をぜひ試してみてください。深呼吸、そして納豆。この二つから始めてみましょう。小さな一歩が、禁酒の成功を大きく引き寄せます。
僕の真の問題は飲み始めると止まらないことですが、最悪の事態を防ぐために「飲んでも1杯だけ」といったルールも検討しています。飲酒欲求は必ず弱まると信じています。
だるさが改善されたら、次は自己投資なんかに時間をあてるのもいいかもしれません。禁酒することで、お金っと時間の余裕が生まれます。
僕たち20代後半〜30代の介護職にとって、だるさの解消は将来の不安解消に直結します。禁酒で生まれた時間と余裕を、僕がどのように投資や自己成長に繋げているかは、【禁酒の効果】禁酒は最高の自己投資だった!お金と時間でスキルアップする方法で紹介しています。
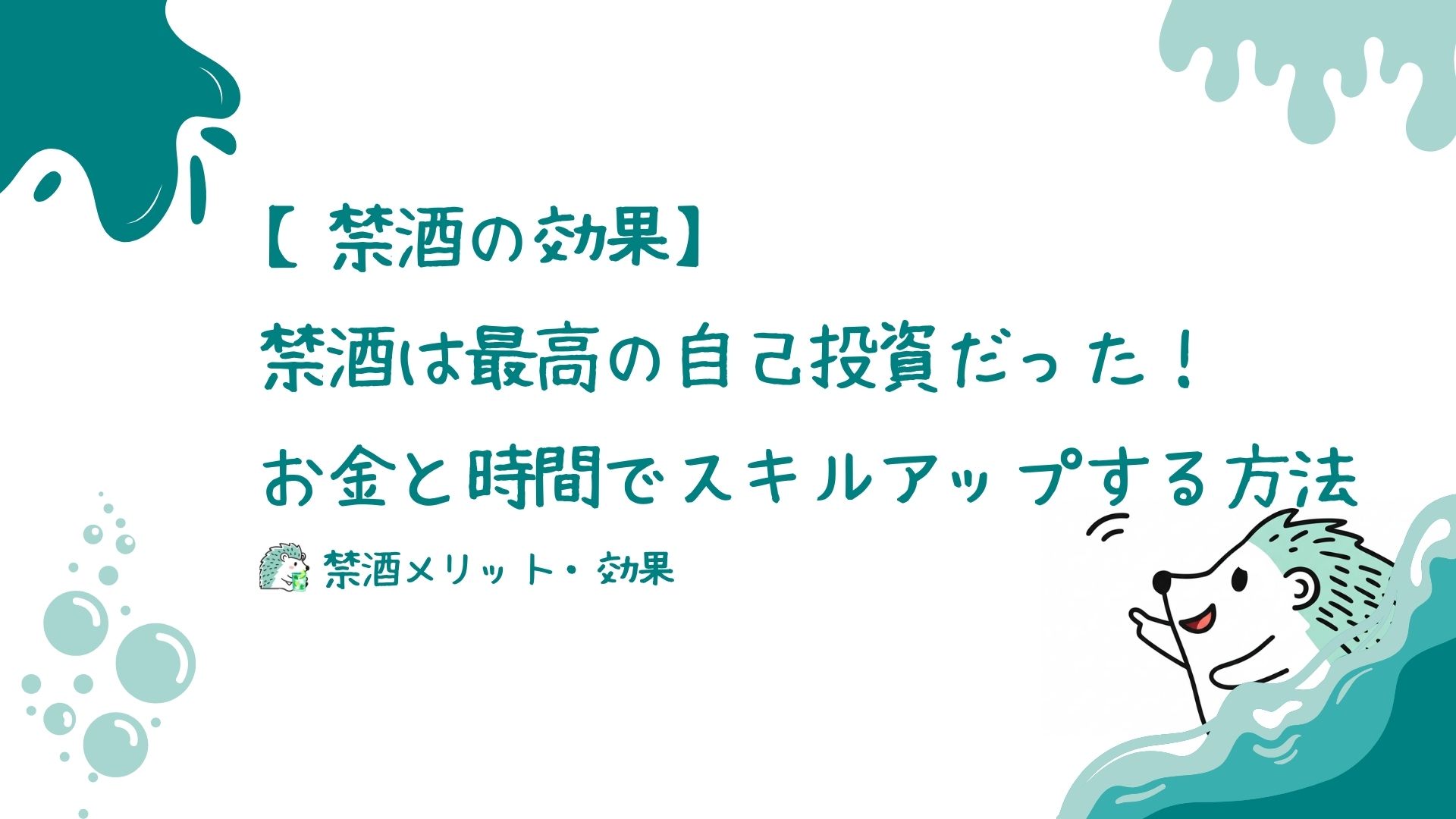
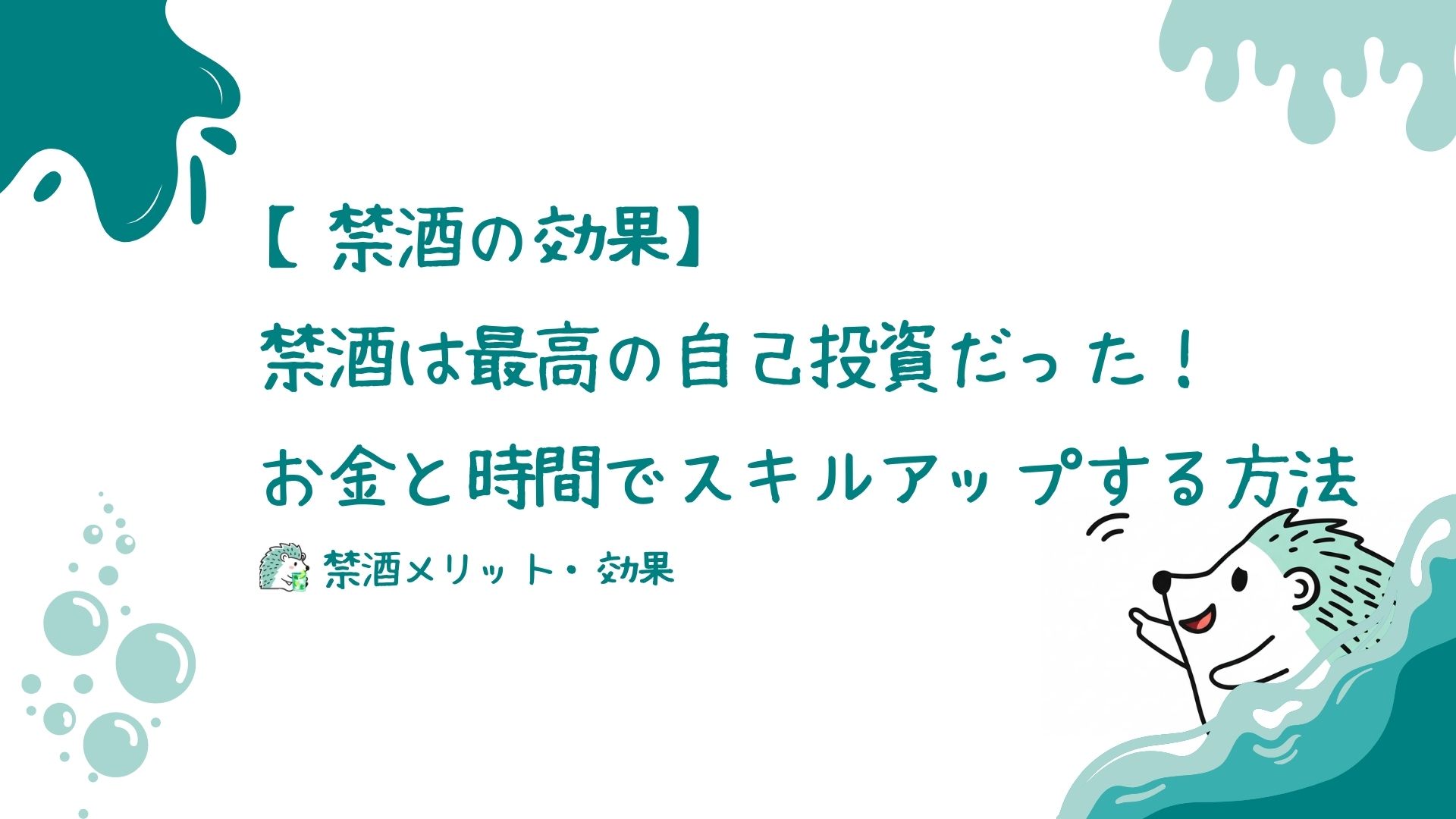
そして、僕が禁酒でできた時間とお金でやっているのが、投資・資産形成です。始めた理由は、年金だけでは老後に不安があったこと、実質賃金が30年低下している等いろいろと将来に不安があったからです。今の僕の目標は、安定して月10万円を投資に回し続けることです。
路上で寝るような浪費癖を直すためにも、お金の管理は必須です。失敗も多いですが、僕と同じようにお金や時間に余裕がないと感じるなら、スマホで5分でできる簡単なことから資産形成を始めませんか?
僕が実際に始めている初心者向けの投資商品(投信・ETF)や口座開設のステップを覗いてみませんか?
詳しくは、【禁酒の効果】貯金だけじゃもったいない!浮いたお金で始める、未来を変える「投資」の話で紹介しています。
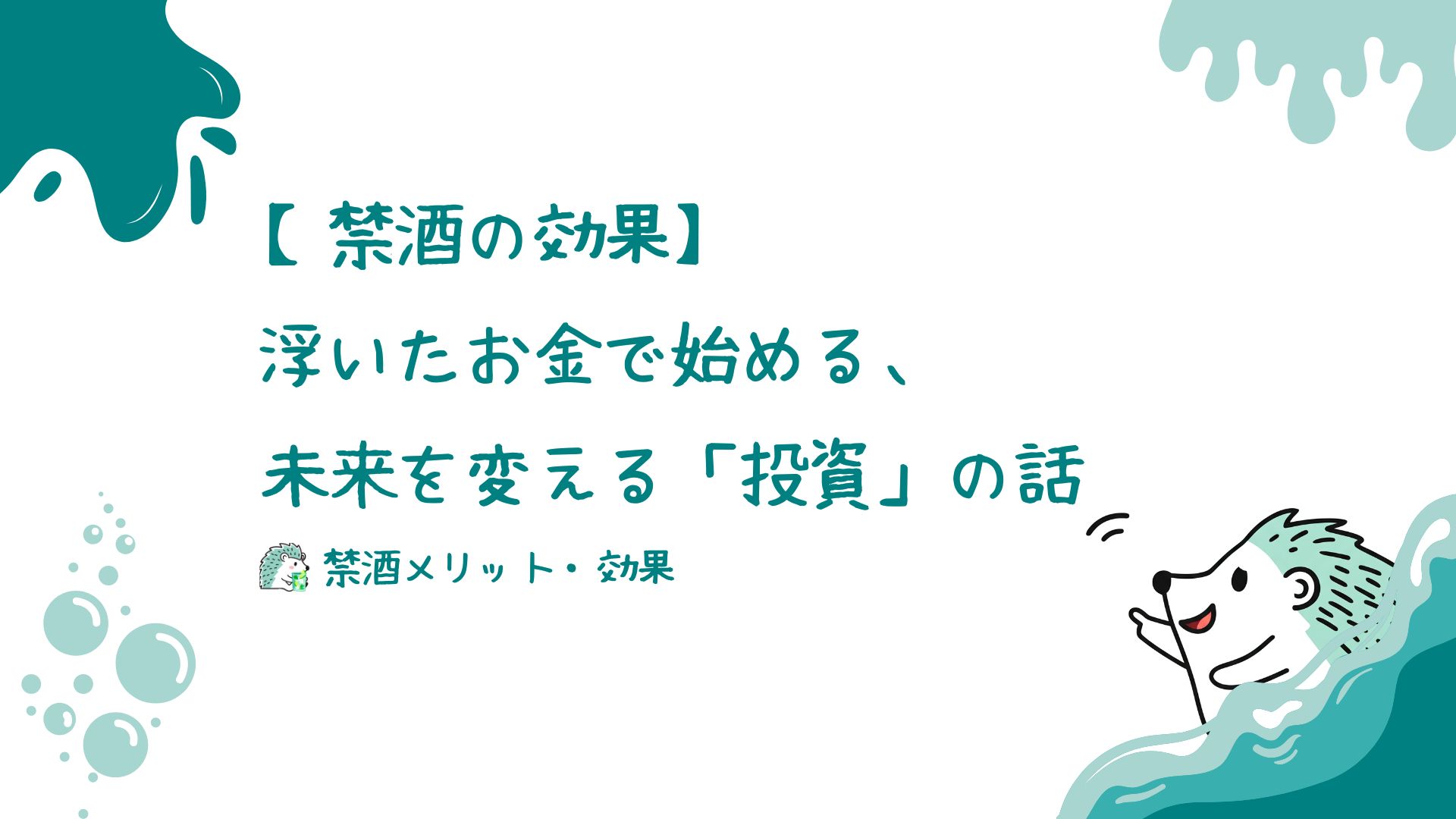
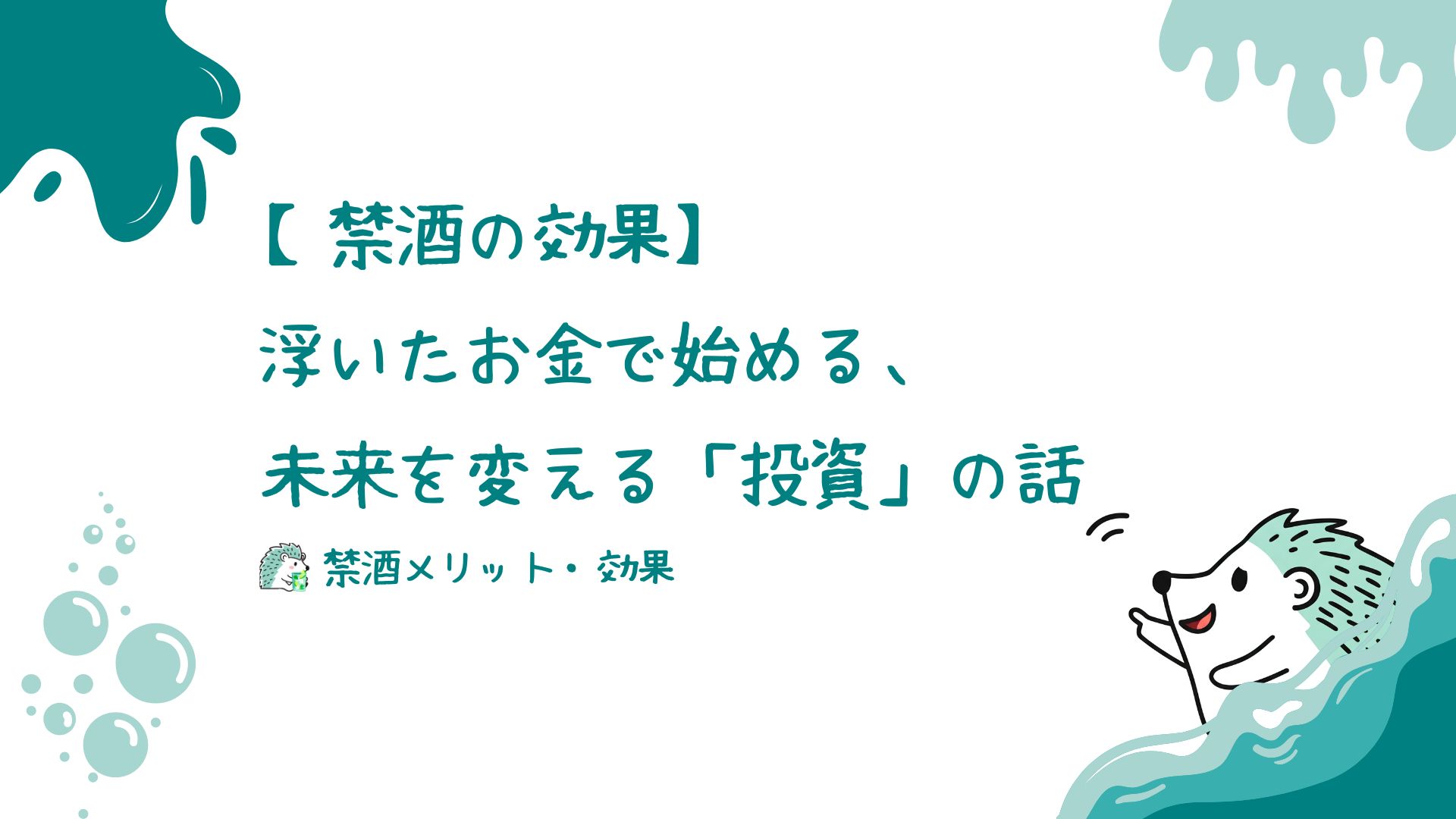



僕も、完璧な禁酒はできていません。でも、「納豆を食べる」「自分を責めない」という小さな工夫で、自己肯定感を保てるようになりました。あなたも、自分に優しく、少しずつ変化を起こしていきましょう。
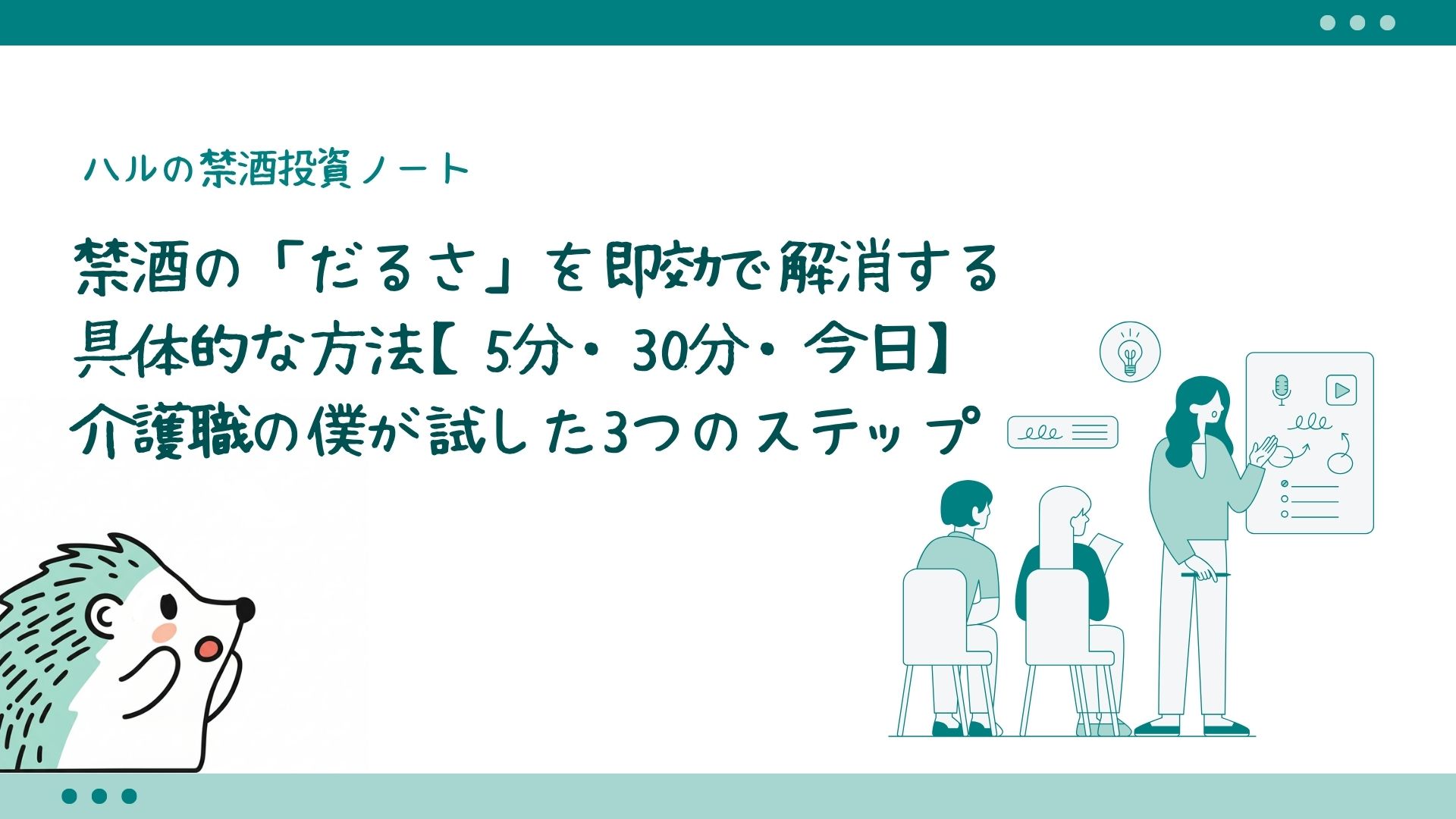
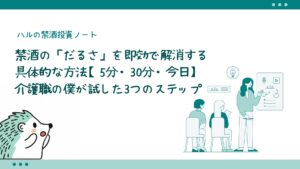

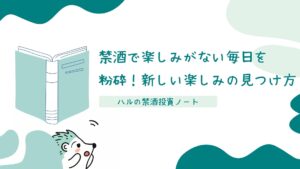
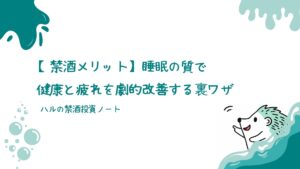
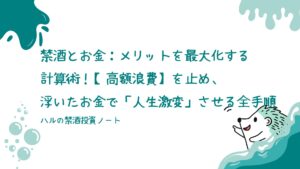
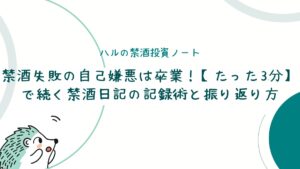
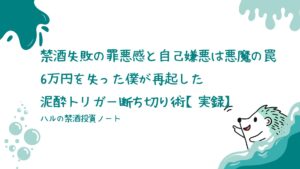
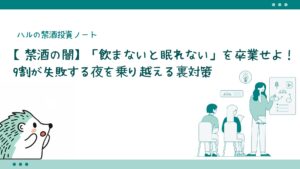
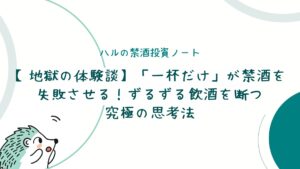
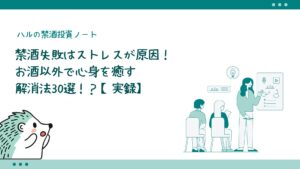
コメント