「お酒を飲まないと、翌朝の体が重い…」「寝ても寝ても疲れが取れない…」って、心から共感します。
特に夜勤もある介護職の僕は、20代から30代にさしかかる頃には、慢性的な睡眠不足と疲労に悩まされていました。
「休肝日をつくろう」と思っても、つい寝る前に一杯飲んで、結果的に睡眠の質は最悪、日中の集中力はガタ落ち…、そんな日々を送っていたんです。
でも、お酒をやめてみて、僕の睡眠の質は劇的に改善しました。
- 禁酒が睡眠に与える「科学的なメリット」と「僕のリアルな体験」がわかります。
- 僕のような「お金も時間もない方」でも実践できる具体的な睡眠改善策が得られます。
- 増えた睡眠時間と集中力を、どう「自己投資や趣味、生活の質の向上」に繋げるかの具体的なヒントが見つかります。
 ハル
ハルこの記事を読んで、もう「寝不足でだるい自分」にサヨナラしませんか?
禁酒で【時間と集中力】を生む!睡眠改善による4つの実質メリット
僕が禁酒を続けてみてわかったのは、お酒をやめることが、ただ健康になるだけではなく、「お金」と「時間」を生み出すための最優先事項だということです。
特に睡眠の質改善は、疲労感や集中力不足という、僕が抱える最大の悩みを解決してくれました。
- 深い睡眠が増え、短時間でも疲れが取れる
- 慢性的な疲労感が消え、体が軽くなる
- 夜の2〜3時間が「自己投資のゴールデンタイム」に変わる
- 日中の集中力が安定し、仕事のミスが激減する
深い睡眠(ノンレム)時間が激増
アルコールには入眠を早める作用があるため、「寝酒」として愛用している人も多いですよね。
僕もそうでした。ですが、これは大きな勘違いなんです。アルコールは睡眠薬とは違い、最も重要な「深い睡眠(ノンレム睡眠)」を激しく阻害してしまいます。
この深い睡眠こそ、脳と身体の疲労回復に欠かせません。僕の場合、禁酒を始めてから、朝起きた時の「ああ、よく寝た」という感覚がまるで違ってきました。
深い睡眠が増えたおかげで、短時間でも熟睡できたと感じるようになっているんですね。
アルコールは一時的に寝つきを良くする鎮静作用がある一方で、疲労回復に不可欠な深い睡眠(ノンレム睡眠)を抑制してしまうことが、睡眠科学の分野で広く知られています。
翌日に疲労を残さない脳の回復法
お酒を飲むと、体内でアルコールが分解される過程で様々な物質が消費されます。
特に質の悪い睡眠は、脳の疲労回復を妨げ、慢性的なだるさにつながるんです。禁酒をすることで、この脳の疲労回復がしっかり行われるようになりました。
僕自身、「週末に疲れをリセットしなくても、平日の疲労が翌日に持ち越されない」という変化を感じています。これにより、毎日安定したコンディションで仕事に取り組めるようになりました。
質の悪い睡眠は、脳の疲労を十分に回復させず、翌日の慢性的な疲労感やだるさに繋がると言われています。アルコールを断つことで、脳の疲労回復が促されると考えられます。
夜の「ダラダラ飲み」を自己投資へ
お酒を飲むと、どうしても体がだるくなり、思考も鈍くなります。僕の場合、自宅で飲むと、それが就寝前の2〜3時間を完全に奪っていました。
この時間は、ただテレビを見て、SNSを見て、そして寝る…という生産性のない時間だったんです。
禁酒をすることで、この時間がそのまま自己投資や趣味のための「ゴールデンタイム」に変わりました。
例えば、寝る前の1時間はスマートフォンを触る代わりに、資格の勉強や趣味の時間に充てることが、何の苦もなくできるようになったんです。
僕の場合、飲酒習慣を見直すことで、平均で週に数時間〜10時間以上の可処分時間が増えました。この時間はスキルアップなどの自己投資や趣味に回すことで充実した生活ができますね。
日中の眠気を消し、集中力UP
質の悪い睡眠は、翌日の日中に「隠れた疲労」として残ります。
これが、会議中の急な眠気や、重要なタスクでの凡ミスに繋がってしまうんですよね。
僕も、仕事中のちょっとした瞬間に集中力が途切れることが悩みでした。禁酒で睡眠の質が改善されてからは、日中の眠気が嘘のようになくなりました。
常に安定した集中力を保てるようになり、以前よりも仕事の効率が格段に上がったと感じています。この安定感こそが、忙しい会社員が資産形成のための「時間」を生み出す鍵だと気づきました。
睡眠の質が安定すると、日中の集中力が向上し、仕事でのミス率が低下するといった研究結果が示されています。
スタンフォード大学の研究では、1時間の睡眠不足が平均的な作業効率を15%低下させるというデータもあるそうですよ。



禁酒で得られるのは「睡眠時間の確保」ではなく、「睡眠の質の向上」による「活動時間の質」の向上、これに尽きるんです。
忙しい介護職が実践!疲労を効果的に取る回復法
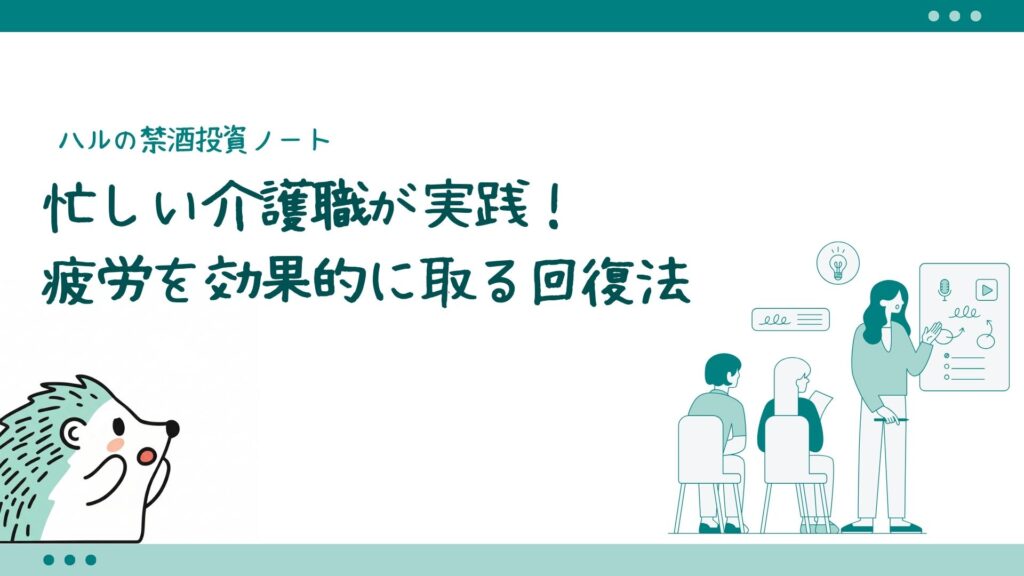
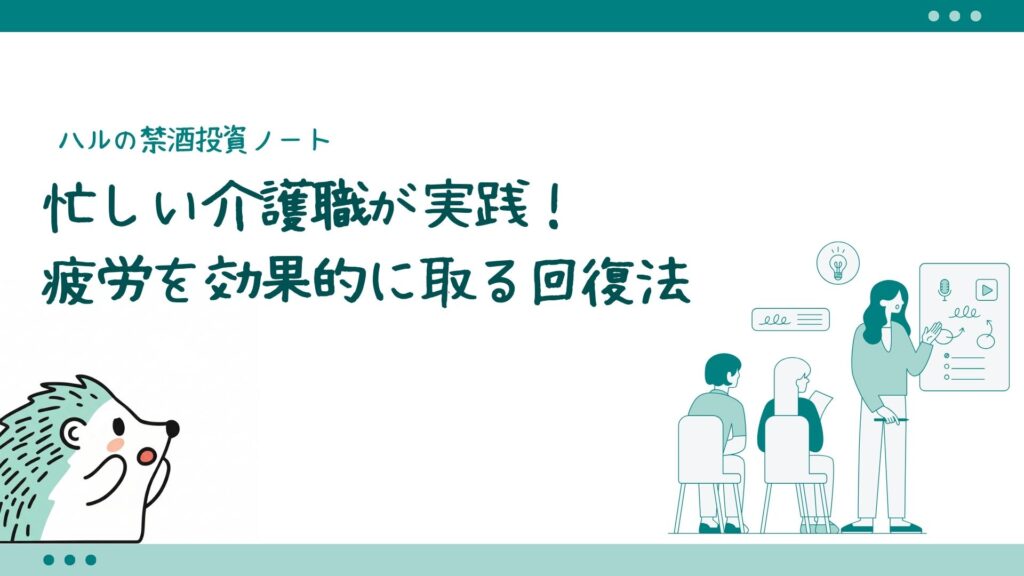
僕のような介護職にとって、睡眠の質改善は仕事の質と安全に直結する問題です。禁酒のメリットは、「最初の1週間〜2週間」で夜間覚醒の減少という形で体感し始められます。
そして、最も重要なのは、「日中のパフォーマンス向上」という形で結果が出ることなんです。
- 禁酒1〜2週間で夜中に目が覚める回数が激減
- 夜勤明けでも短時間仮眠で体が回復できる
- 仕事中の誤薬やケアミスの恐怖から解放される
- スマートウォッチで「レム睡眠」割合をチェックできる
1〜2週間で夜間覚醒が激減
アルコールの覚醒作用がなくなるため、禁酒開始から1週間〜2週間ほどで、「夜中に目が覚めにくくなったな」という変化を明確に感じ始めることができます。
僕のリアルな経験でも、夜中に目が覚める回数が4回くらいから1回くらいに減ったことをはっきりと覚えています。夜中に一度も起きない日が増えたことが、禁酒継続の大きな自信につながったんです。
アルコールの分解産物であるアセトアルデヒドには覚醒作用があるため、これがなくなることで、禁酒開始後比較的早い段階(数日〜1週間)で中途覚醒が減少する傾向にあるといったデータがあります。
夜勤明けは「3時間仮眠」で回復
禁酒前、夜勤明けは「みんなが働いている時間に酒が飲める最高」などと間違った価値観で飲んでしまい、夜の8時頃に目が覚める昼夜逆転が当たり前でした。
しかも、翌日まで疲労感が抜けなかったんです。それが今では、夜勤終わりに3時間仮眠を取るだけで体が回復するようになり、その後の時間を自由にブログを書くなどの活動に充てられるようになりました。
質の高い睡眠は、夜勤明けの貴重な自由時間を生み出してくれるんです。
飲酒による睡眠は、レム睡眠の減少などにより翌日の疲労感が残りやすいと考えられます。質の良い睡眠をとることで、夜勤後の回復に必要な時間が短縮されるみたいです。
介護職の誤薬リスクがゼロに
睡眠の質が改善したことで、日中のパフォーマンスが劇的に向上しました。
一番大きかったのは、会議などで眠くならなくなったことです。以前は、ひどい二日酔いで仕事をして帰らされた経験(はずい(/ω\))もありますし、利用者の車椅子からベッドへの移乗も二日酔いの時は本当につらかったんです。
特に介護職として最も怖いのが誤薬で、命に関わるレベルのリスクです。服薬介助の時に、以前よりもはっきりと集中して取り組めるようになったのは、禁酒のおかげだと断言できます。
睡眠不足は集中力や判断力を低下させることが専門家の間では広く知られています。介護などの高い集中力を要する仕事において、睡眠の質向上がミスの予防に繋がると言われています。
睡眠の質は「レム睡眠」割合で確認
僕もスマートウォッチなどで自分の睡眠データをチェックするようにしました。記憶の整理や感情の処理を行う「レム睡眠」は、アルコールによって大きく削られてしまいます。
禁酒を続けると、このレム睡眠の割合が正常に戻ってきます。僕自身、禁酒後に新しい情報(スキルアップの知識など)が頭に入りやすくなったと感じるのは、このレム睡眠がしっかり取れているからかもしれませんね。
記憶の整理を行うレム睡眠は、アルコールによって大きく抑制されることが研究で示されています。禁酒によりレム睡眠が回復し、学習効率が上がる可能性があると考えられます。
夜中に目が覚める回数が4回くらいから1回くらいに減ったことを、禁酒開始1週間〜2週間で明確に体感しました。
夜勤明けは、以前の「みんなが働いている時間に酒が飲める最高」などと間違った価値観での飲酒がなくなり、3時間仮眠で体が回復。午後の時間をブログ作業などの自己投資に充てられるようになりました。
また、ひどい二日酔いで仕事に出て帰宅させられた経験がある僕にとって、禁酒で服薬介助の時の誤薬の恐怖から解放されたのが、精神的に一番大きかったです。
帰らされた失敗はほんと隠したいくらい恥ずかしいですわ。かいちゃってるけどさ



僕にとって、質の高い睡眠は、介護職の仕事の質と安全に直結する最大の自己投資でしたね。
禁酒で眠れない不安を解消!最高の睡眠継続期間


アルコールに頼っていた体が、急にアルコールを断つと、一時的に寝つきが悪くなることは珍しくありません。
これは、体が自力で眠るリズムを取り戻そうとする「調整期間」なんです。この期間を乗り越えるために、僕は「睡眠を誘う行動」に意識的に取り組む必要があります。
最高の睡眠を安定して手に入れるには、最低でも1ヶ月間は継続し、新しい習慣を定着させることが大切なんです。
- 一時的な不眠には「温かい飲み物」で新習慣を作る
- 寝る1時間前からスマホ・PCを完全に遮断する
- 「一駅歩く」など、日中に適度な疲労を作る工夫
- 最高の熟睡には「最低1ヶ月間」の継続が必須
不眠には「温かい紅茶」で新習慣
これまで、お酒を飲むことが「寝る前の儀式」になっていた人も多いはずです。
その代わりとなる新しいリラックスの習慣を作ることが、スムーズな入眠につながります。
僕にとって最も効果的だったのは、あったかいミルクティーを飲むことでした。これを毎日繰り返すことで、
「 紅茶を飲む ⇒ 布団に入る ⇒ 寝る 」
という思考回路が勝手に働くようになり、習慣化の力を実感できました。飲み物を固定することも大事だと気づいたんですよ。
寝る前のルーティン(儀式)は、脳に睡眠の準備をさせるための条件付けとして有効だと考えられています。特に温かい飲み物は、副交感神経を優位にする効果があると言われています。
寝つきを良くするスマホ遮断法
スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトは、僕たちの体を眠りに誘う「メラトニン」というホルモンの分泌を抑制してしまいます。
禁酒で寝つきが悪くなったと感じたら、まずは寝る1時間前からはスマホを見るのをやめる、というルールを厳格に守ってみてください。
僕も自己投資などで夜遅くまでパソコンを使うことがありますが、寝る直前には必ず画面を閉じるようにしています。代わりに、本を読んだり、ラジオを聴いたりする時間に変えるのがおすすめです。
スマートフォンなどから発せられるブルーライトは、睡眠を誘うメラトニンホルモンの分泌を抑制することが広く知られています。就寝1時間前からの使用は控えることが推奨されています。
寝るために必要な「適度な疲労」
不眠は、単に夜の問題だけでなく、日中の過ごし方にも影響されます。適度な運動は、夜に体をスムーズに眠らせるための自然な疲労を生み出します。
激しい運動はかえって交感神経を刺激してしまうので、夕方以降は避けるべきです。僕がやっているのは、「帰宅時に一駅分歩く」ことや、「寝る2時間前までに軽めのストレッチを行う」ことです。
この「軽い疲労」が、夜の寝つきを劇的に良くしてくれるのを実感しています。
日中の適度な運動は、夜間の深部体温の低下を促すなど、睡眠の質を改善する効果があることされています。ただし、就寝直前の激しい運動は避けるべきみたいです。
最高の熟睡は「最低1ヶ月」継続
最高の睡眠の質を手に入れるには、最低でも1ヶ月間、できれば2ヶ月間は禁酒を続ける必要があります。
体がアルコールに依存しない状態に完全にリセットされ、自然な睡眠リズムが定着するのに、このくらいの期間が必要だからです。
僕自身も、寝つきに関しては禁酒前と変わらず20分程度で眠れているのですが、やはり短期的な不眠に悩まされず、長期的視点で取り組むことが大切なんです。
不眠で「オールで仕事か…だりー」と不安に感じたり、「酒飲みたくなったり」することもありましたが、なんとか乗り越えることができました。
アルコールを常用していた方が禁酒をすると、一時的に寝つきが悪くなるなどの好転反応が出ることがあります。睡眠の質が完全に安定するまでには、1〜2ヶ月間の継続が理想的だと考えられています。
禁酒で一時的に寝つきが悪くなった時は、「オールで仕事か…だりー」と疲労への懸念と不安を感じました。そして「眠れないなら酒が飲みたい」という葛藤もありました。
しかし、そこで「寝る前の儀式」として温かいミルクティーを飲むことに。これにより、「紅茶を飲む⇒布団に入る⇒寝る」という新しい習慣ができ、眠れない不安を乗り越えることができました。



最高の熟睡は「1ヶ月の継続」から。温かい飲み物で新しい入眠習慣を作りましょう。
睡眠の質を「最大化」する!寝室・入浴の黄金ルール


睡眠の質は、「体内リズム(時間)」と「寝室の環境(場所)」によって決まります。
禁酒で体内リズムは整いやすくなりましたが、さらに質を高めるために、寝室を「眠るためだけの最高の空間」に作り変える工夫が必要なんです。僕が特に意識したのは、「光の遮断」と「寝る前の体温調整」でした。
- 遮光カーテンやシールで寝室の「光」を徹底遮断
- 寝る1.5〜2時間前の入浴で深部体温をコントロール
- 枕を見直して首・肩の痛みを解消する
- 午後3時以降のカフェイン摂取をストップする
熟睡を呼ぶ寝室の「光」遮断術
人は、光を感じると目覚めのホルモン(セロトニン)が分泌されます。寝室にわずかでも光が差し込むと、睡眠の質は低下してしまうと言われています。
僕が実践したのは、「遮光カーテンの導入」や、「遮光シートを窓に貼る」という徹底的な光の遮断です。特に、夜勤明けの休日に昼間寝る時は、この光の遮断が深い眠りを誘ってくれます。
ちょっとした工夫ですが、効果は絶大なんですよ。
睡眠中にわずかな光でも入ると、睡眠の質や持続時間が低下する。寝室は真っ暗にすることが、メラトニン分泌のために重要だと言われています。
入眠を誘う「入浴の黄金時間」
人は、体の中心部の体温(深部体温)が下がるときに眠気がやってくるようにできています。
熱いお風呂に入って体温を上げた後、それが急激に下がるタイミングで眠気を誘うのが理想なんです。
僕の経験では、寝る1時間半〜2時間前に、少しぬるめのお湯(38〜40℃)にゆったり浸かるのが最も効果的でした。禁酒で時間に余裕ができたからこそできる、最高のルーティンだと思っています。
就寝の90分前(1.5時間前)に40℃程度のぬるめのお湯に浸かるのが、深部体温を効果的に下げ、入眠を誘うための黄金ルールだとされています。
枕を変えて首・肩の痛みを解消
睡眠時間の約3分の1を過ごす寝具は、「疲れが取れるか」を左右する最も重要な要素の一つです。
どんなに環境を整えても、体に合わない寝具では深い眠りは得られません。
僕の場合、3点セットで売っていた枕から、ふかふかでボリュームのある枕に変えてみました。
すると、寝起きに肩や首が痛くなっていたのがなくなったんですよね。寝具はすぐに全て変えるのは難しいかもしれませんが、まずは枕だけでも自分の体に合ったものに変えてみるのがおすすめです。
枕が合わないと、首や肩の緊張、血行不良を引き起こし、睡眠の質を低下させると考えられます。自分に合った寝具選びは、疲労回復に直結すると言われています。
眠りを妨げるカフェインを断つ
アルコールだけでなく、カフェインやニコチンも睡眠を阻害する大きな原因です。
カフェインには覚醒作用があり、寝る直前の喫煙は交感神経を刺激してしまいます。僕も仕事中はコーヒーを飲むことが多いですが、午後3時以降はノンカフェインの飲み物に変えるように徹底しました。
禁酒と合わせて、これらの刺激物も断つことで、睡眠の質の向上効果が相乗的に高まることを実感しています。
カフェインは摂取後数時間は覚醒作用が続くため、一般的に午後2時〜3時以降の摂取は控えるべきだという意見があります。ニコチンも交感神経を刺激します。
以前は3点セットの枕を使っていて、朝起きると首や肩が痛いことがよくありました。
そこでふかふかでボリュームのある枕に変えたところ、それが解消しました。寝具は投資効果抜群だと感じています。
入浴は寝る1時間半前に済ませて、体温が下がるタイミングで布団に入るようにしてみたんですけど、これが効果的で寝つきが全然違くてよかったです。



最高の寝具と環境は、お金がない僕たちにとって、生産性を上げる最高の投資になるんです。
なぜ飲まない方が熟睡できる?科学的な理由


お酒を飲んで感じる「眠気」は、「脳が麻痺している状態」に近く、本来の自然な眠りではありません。
アルコールが脳に作用し、一時的に意識レベルを下げることで眠気を感じるだけなんです。
この人工的な眠りは、僕の体を休めるために最も重要な、「睡眠の質」を根本から破壊してしまいます。
- 疲労回復に必須な深い睡眠をアルコールが阻害する
- 記憶力を支えるレム睡眠の出現が遅れる
- アルコールの分解で体温が上がり、眠りが浅くなる
- 強い利尿作用で夜中にトイレに起きてしまう
深い睡眠を阻害するメカニズム
アルコールは、中枢神経に作用して一時的に鎮静作用をもたらします。これにより「寝つきが良くなった」と感じるのですが、問題はその後です。
アルコールが体内にあると、脳は深い睡眠である「ノンレム睡眠」にスムーズに入れなくなってしまうと言われています。
僕も以前はすぐに眠れていましたが、朝のダルさが異常でした。禁酒後、すぐに眠れなくても、深い眠りに入れているからこそ、翌朝の爽快感がまるで違うんです。
アルコールは、寝つきは良くするものの、睡眠後半の深い睡眠を減少させ、覚醒状態を増やしてしまうことが知られています。
記憶力を下げる「レム睡眠」減少
睡眠には、深いノンレム睡眠のほかに、体は休んでいるけど脳は活動している「レム睡眠」があります。
これは、日中の出来事や学んだ知識を整理し、記憶として定着させるためにとても重要な時間です。アルコールは、このレム睡眠の出現を遅らせたり、時間を短縮したりすることが分かっています。
自己投資をしている僕にとって、レム睡眠が削られるのは致命的です。禁酒でレム睡眠が回復し、集中力や記憶力が上がったのも、これが大きな理由だと感じています。
飲酒は、記憶の定着や感情の調整に重要なレム睡眠を抑制してしまうと言われています。
夜中に体温が上がり眠りが浅くなる
アルコールが体内で分解される際、熱が発生するため、寝ている間に体温が上昇してしまいます。
前述したように、体温が下がる時に眠気が誘われるため、寝ている途中で体温が上がってしまうと、睡眠が浅くなり、途中で目覚める原因となるんです。
僕も夜中に暑くて目が覚めることがよくありましたが、禁酒後はそれがほとんどなくなりました。
アルコールの分解に伴う体温上昇は、睡眠中の体温低下リズムを乱すため、睡眠を浅くしたり、途中で目覚める原因になったりすると考えられています。
利尿作用で夜中にトイレに起きる
アルコールには強い利尿作用があるため、水分を多くとってもいなくても、夜中にトイレに行きたくなって目が覚めることが増えます。
これでせっかくの睡眠が途切れてしまうんです。僕も夜中にトイレで目が覚めてしまうことが度々あり、その後の寝つきが悪くなることに悩んでいました。
禁酒をすれば、この利尿作用も当然なくなります。朝まで一度も起きずにグッスリ眠れることが、こんなにも快適なんだと改めて実感しています。
アルコールには強い利尿作用があり、これが夜間の排尿回数を増やし、中途覚醒の原因になることが指摘されています。
以前は「みんなが働いている時間に酒が飲める最高」などと間違った優越感に浸って飲酒していました。
しかし、飲酒で寝ると夜中に暑くて何度も目が覚める上、翌日まで体のだるさが抜けず、昼夜逆転という最悪の悪循環に陥りました。「眠れた気になる」のと「本当に休めている」のは、全く違うことを痛感しました。



お酒の「眠気」は偽物の眠り。体と脳を真に休めるには、禁酒は科学的に正しい選択なんです。
集中力が爆上がり!自己投資に充てた具体的な時間
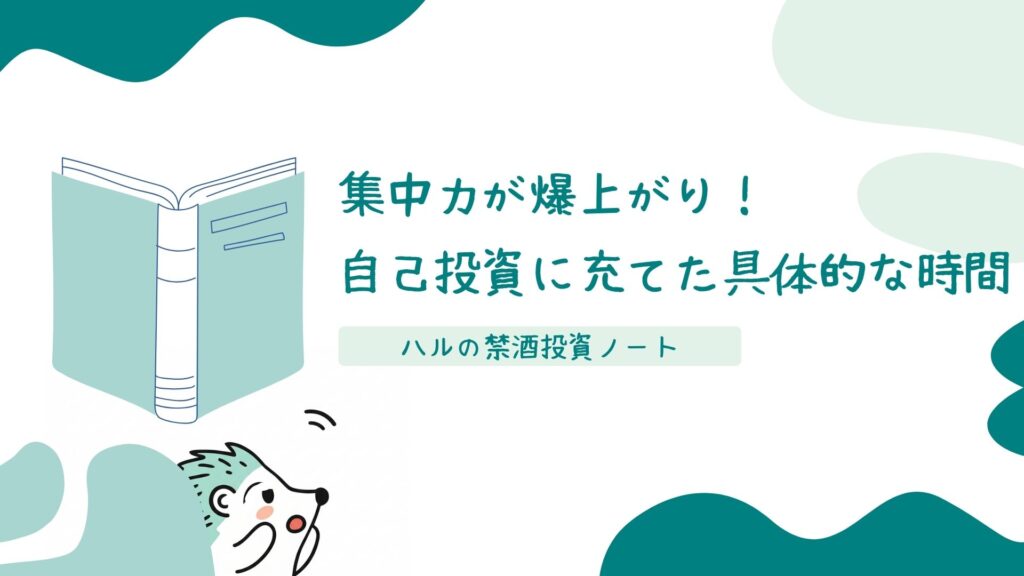
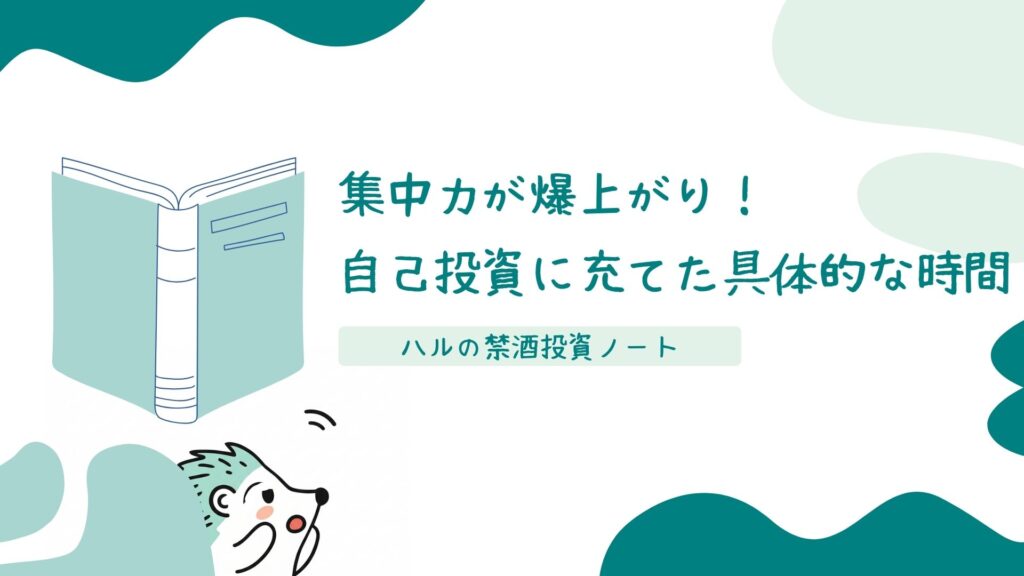
僕のようなお金に余裕のない方にとって、自己投資のための「時間」は、お金以上の価値があります。
禁酒する前は、夜のお酒と翌日の二日酔いで、平日の自己投資時間はほぼゼロでした。
ですが、禁酒を始めて睡眠の質が安定してからは、「平日の夜」と「休日の午前中」に生産性の高い時間を確保できるようになったんです。
- 禁酒前はゼロだった平日の集中時間を確保
- 休日の午前中2〜3時間を自己投資に充てる
- 「25分集中→5分休憩」の短時間作業術で集中力を維持
- 寝酒で休日を丸ごと潰した失敗談と教訓
平日の夜に「集中タイム」を確保
禁酒前は、帰宅後の19時〜20時頃によく晩酌を始めていました。この時間帯は習慣として体が飲みたがる時間なので、あえてこの時間帯に自己投資の集中タイムを設定し、習慣の上書きを意識しました。
最初は1時間も集中力が持ちませんでしたが、1ヶ月も経つと、1時間で終わらずに2時間、3時間と集中してブログの作業ができるようになりました。この集中力は、睡眠の質が上がった証拠だと感じています。
習慣化を意識して決まった時間に作業することで、脳がその時間を活動モードに切り替えるようになり、集中力を持続させやすくなります。僕の体験では1か月もすれば、特に苦も無く継続できるようになりました。
休日午前を「自己投資」に転換
禁酒で睡眠の質が安定したことで、二日酔いで潰れていた休日の午前中が、「生産性の高い時間」へと劇的に変わりました。
以前は昼過ぎまで布団の中でゴロゴロしていたんですが、今は朝9時にはスッキリ目覚めて活動を始められます。
この「休日の午前中」に2〜3時間まとめて自己投資に充てられるようになったことで、インプットの効率が格段に上がったと感じています。
休日に集中タイムを確保するためにも、前の晩は日をまたがない(0時まで)、できれば21時〜22時には寝るよう意識していました。
最近では、朝活にも挑戦しています。朝6時には禁酒記録のツイートをして、ブログや資格の勉強なんかをやるようにしてますね。これが意外とよくて夜よりも集中して作業ができます。今は習慣化を目標に継続中….
集中力が続く「短時間作業術」
睡眠の質が上がったとはいえ、長時間集中し続けるのは難しいですよね。
僕が実践しているのは、「ポモドーロ・テクニック」のように、「25分集中→5分休憩」という形で作業を区切る方法です。
これにより、短時間でも最大の集中力で取り組めるようになりました。僕の場合、この時間に集中力が必要な作業(ブログや資格の勉強など)を行っています。
この短時間集中の習慣が、僕の自己投資を効率的に進める土台になっています。
ポモドーロ・テクニックなどの短時間集中法は、集中力の維持と生産性の向上に有効であるといった研究結果があります。
寝酒で「休日を丸ごと潰した」失敗
禁酒中に「眠れない日」があり、お酒の力で寝ようとしてしまったことがありました。
ところが、飲んでも全然眠くならず、むしろ止まらなくなってしまい、最終的に朝の6時まで4本も5本も飲み明かしてしまったんです。
当然、起きたのは夕方の4時か5時。楽しみにしていた休日を丸1日潰してしまい、「寝るために飲んだのに意味ねー」と強く後悔しました。
しかも、だるくてご飯を作るのも嫌になり、出前館やUberEatsを頼んで余計な出費がかさみ、自己嫌悪に陥るという最悪の結末でした。
僕の体験から言えるのは、最高の睡眠の質を追求するなら、寝る前の飲酒は「ゼロ回」を目指すのが最も確実だということです。
アルコール依存症は、飲酒量が自分の意思でコントロールできなくなることが特徴の一つです。眠るために飲んだのに量が増えてしまうのは、依存の兆候である可能性も否定できないため注意が必要だとされています。
飲酒で寝ようとして失敗した時の後悔は今でも忘れられません。眠れない日に飲んだら、朝の6時まで4〜5本も飲み明かし、起きたのは夕方4時。休日を丸ごと潰した上に、だるさで出前館やUberEatsを頼んで余計な出費がかさみました。
今は、以前飲んでいた19時〜20時をブログ作業などの自己投資に充て、1ヶ月で2〜3時間の集中作業ができるようになりました。休日は、前の晩0時までには就寝することで、午前中からスッキリ活動できています。



夜の2〜3時間と休日の午前中。このゴールデンタイムこそが、僕たちの未来を創る時間なんです。
まとめ
この記事を通して、禁酒が単なる健康法ではなく、あなたの人生を豊かにするための「最強の時間とお金の作り方」であること、特に「睡眠の質向上」がその土台となることをお伝えしました。
- 深い睡眠が増え、短時間でも疲れが取れる
- 慢性的な疲労感が消え、体が軽くなる
- 夜の2〜3時間が「自己投資のゴールデンタイム」に変わる
- 日中の集中力が安定し、仕事のミスが激減する
酒をやめて、まずは「今夜の睡眠」を変えてみませんか? 今日から寝る前の晩酌をやめ、僕が実践したように温かいミルクティーを飲んでみてはいかがでしょうか。
僕が禁酒に挑戦し、ブログを始めたのは、介護職という給与が低いと言われる仕事でも、将来の不安を解消できることを証明したいからです。
今の日本では、年金だけでは老後生活が厳しいという将来への不安があります。禁酒で生まれたお金と時間を、不安を解消するための自己投資に回すことで、あなたの未来は必ず変わります。
僕も、「暇だとお酒を飲んでしまうから」という理由から、興味のあった投資やブログを始めてみました。
自己投資については、【禁酒の効果】禁酒は最高の自己投資だった!お金と時間でスキルアップする方法で紹介しています。
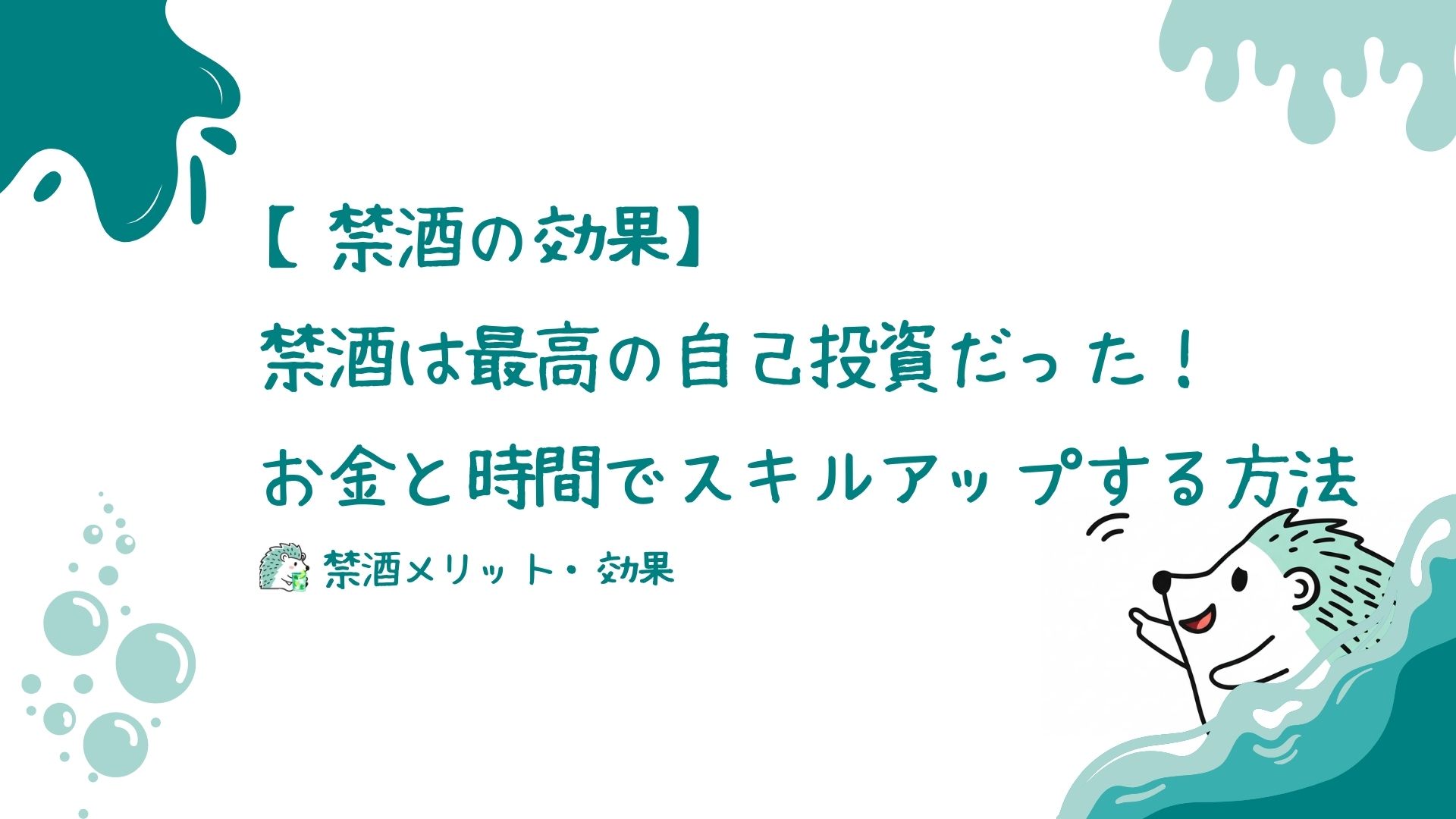
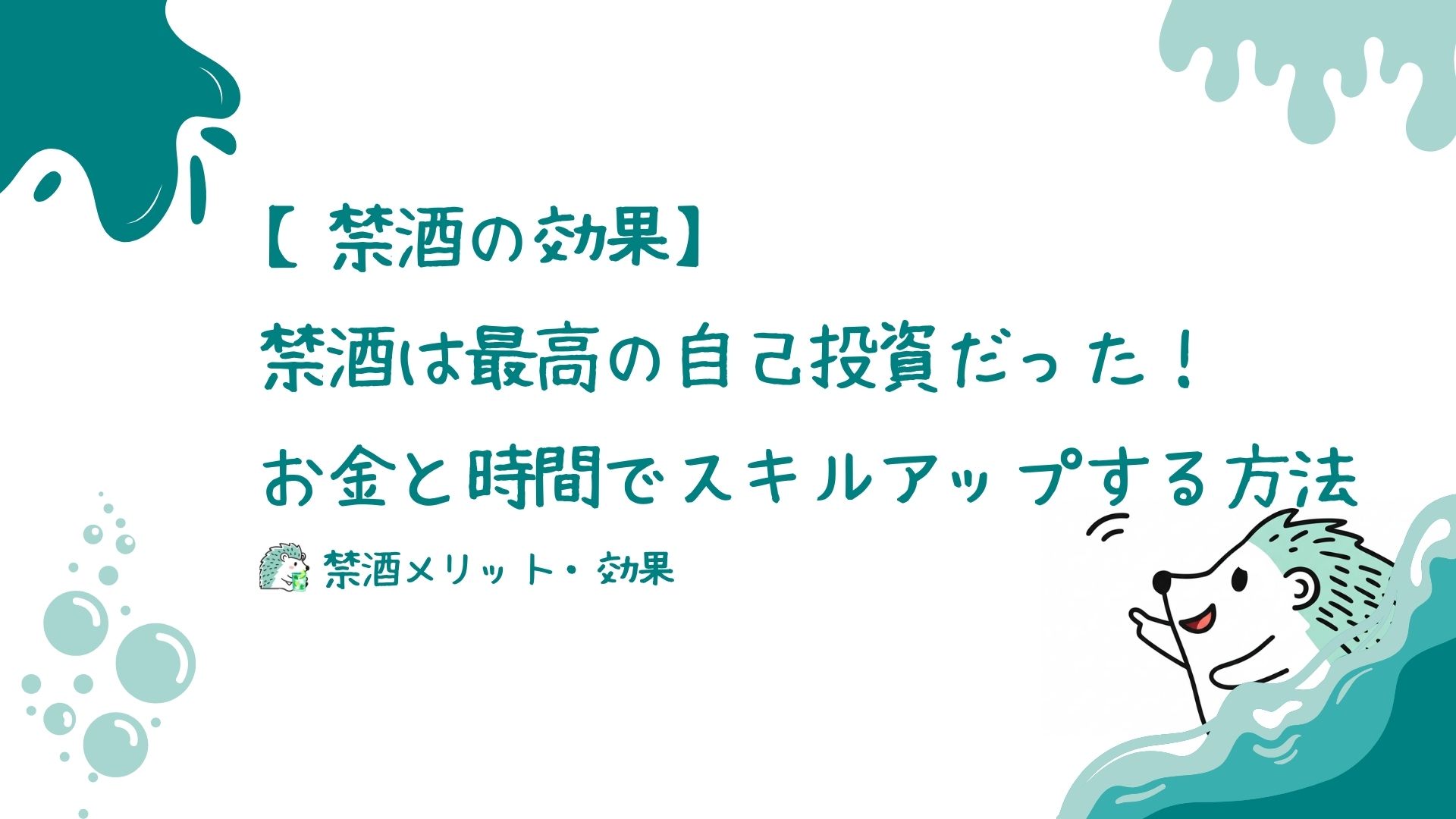
昔の僕と同じように、「投資は難しそう」「お金がないから無理」と、将来への行動をずるずる後回しにしていませんか?
僕も「ずるずる後回しにしていたけど、禁酒を機に行動した」一人です。
実は、スマホで数分あれば、投資を始めるための口座開設は簡単にできてしまいます。 難しいことは考えず、まずは一歩。僕と一緒に、一歩ずつ資産形成を始めませんか?
僕と同じ投資初心者のあなたでも、NISAや高配当ETFなどの仕組みを理解し、手軽に資産形成を始められる方法を【禁酒の効果】貯金だけじゃもったいない!浮いたお金で始める、未来を変える「投資」の話で紹介しています。
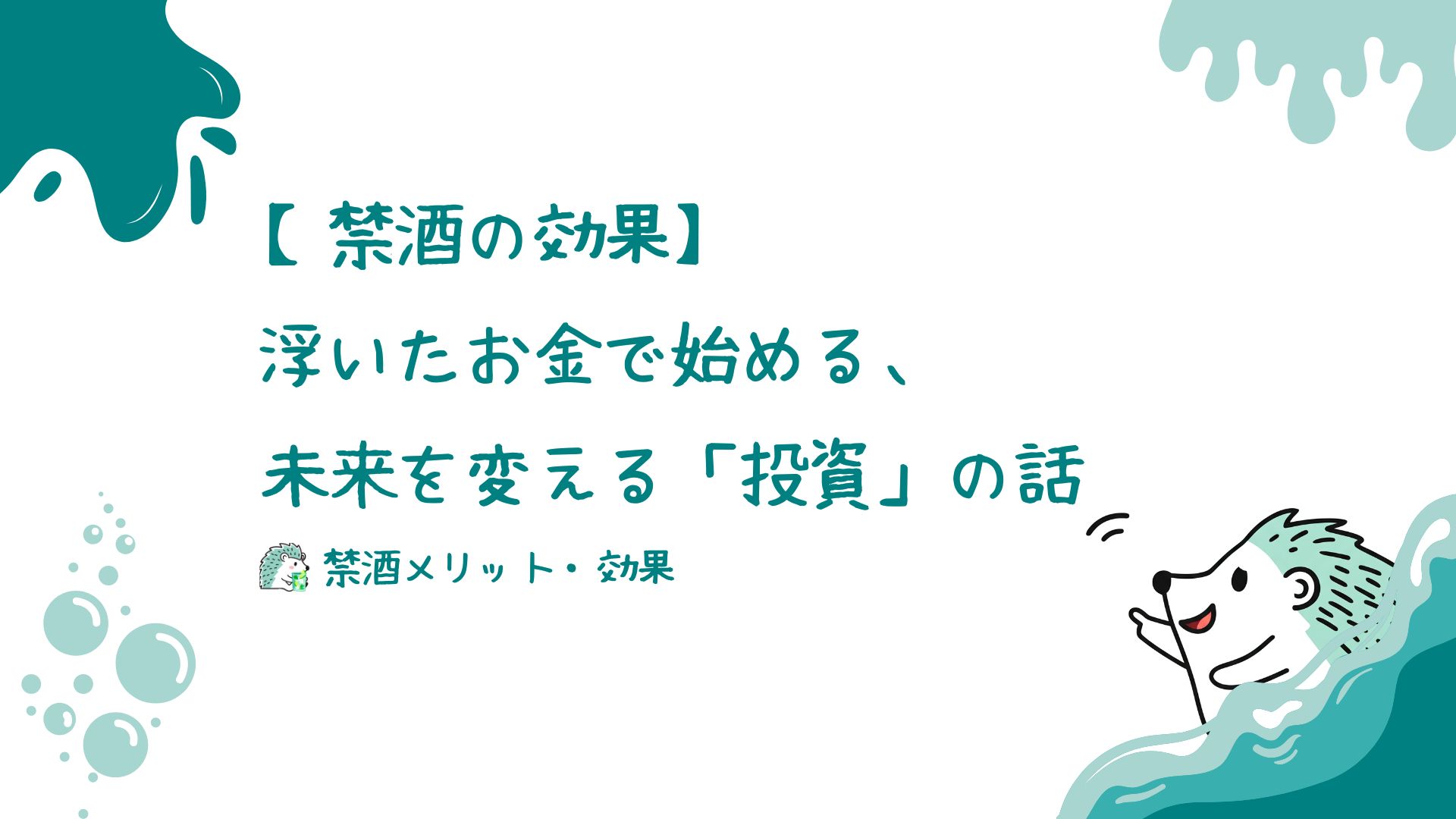
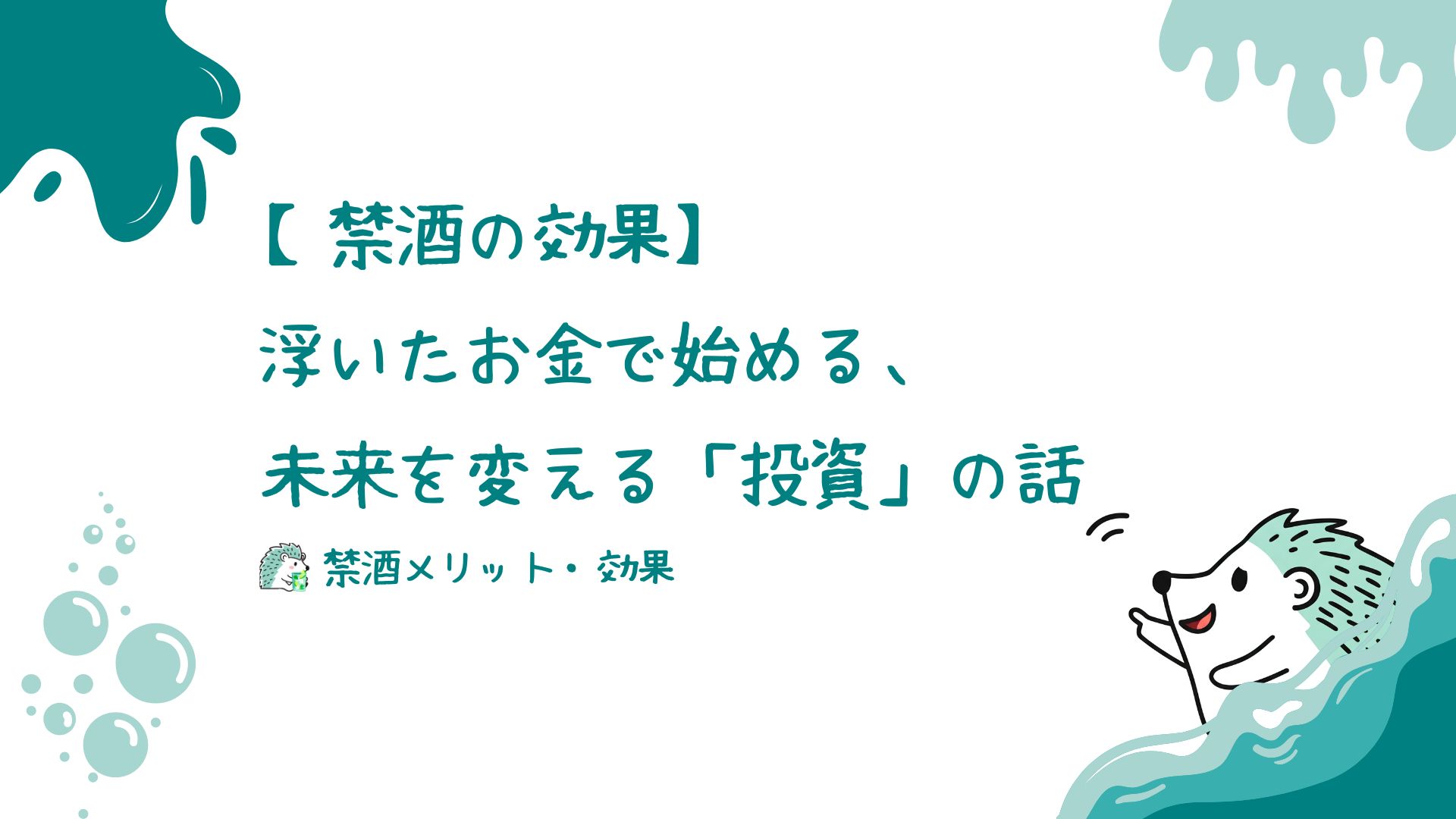



僕もまだ禁酒に挑戦して3ヶ月目の初心者です。僕も失敗を繰り返していますが、僕たちの未来は、僕たちが今、行動するかどうかで決まります。 この辛さを乗り越えたあなたなら、お金に余裕のある未来を必ず掴めると僕は信じています。

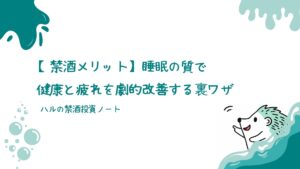

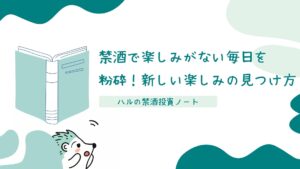
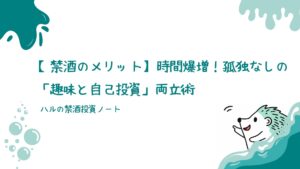
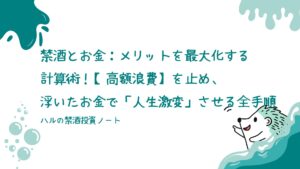
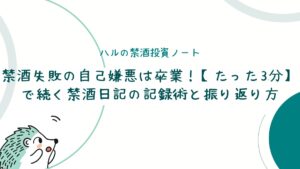
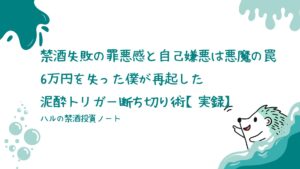
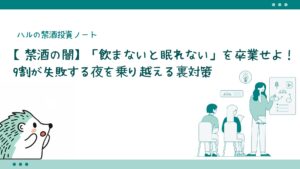
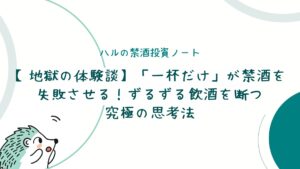
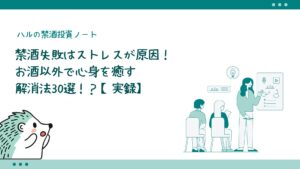
コメント